インターネット上でのストーカー行為は「ネットストーカー」と呼ばれ、実際のストーカー行為と同じような犯罪行為とされています。
SNSの発展に伴って急速に被害が拡大しており、対策は急務となっています。
ネットストーカーの対策においては、どのような準備が必要なのでしょうか。
この記事では、ネットストーカーの対策に向けて被害の内容や事例、効果的な対策方法までをご紹介します。
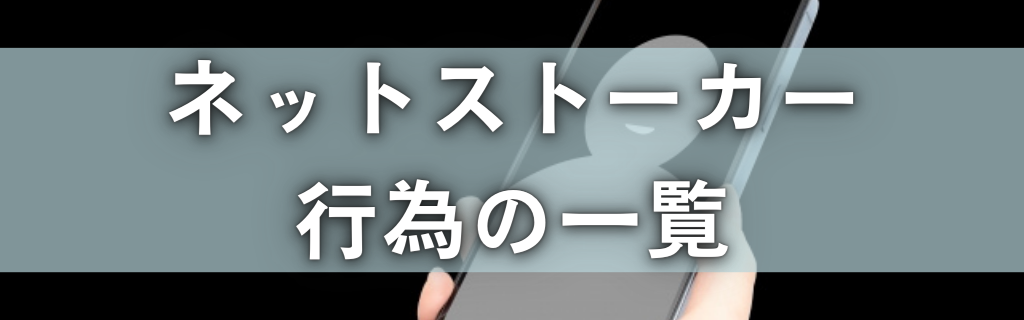
ネットストーカーはどのような行為を行なって犯罪をはたらくのでしょうか。
ネットストーカーが行なうストーカー行為を一覧でまとめましたので、ご参考ください。
ネットストーカーは、少ない手がかりからでも個人情報の割り出しが可能です。
下記のような情報を組み合わせて、個人を特定しようとします。
これらはあくまで一例にすぎません。
情報が至るところに存在するインターネットにおいて、個人の特定はとても容易になっていると認識しましょう。
他人の名義を勝手に使用して情報発信したり、SNSアカウントを運用することをなりすまし行為といいます。
このなりすまし行為も、ネットストーカーによるものです。
なりすまし元の人物の知名度や存在を悪用する意思がなければ、このような行為は行えません。
対象者の持つ影響力を明確に利用するために行なっているといえます。
ネットストーカーは、対象者の利用するスマホやパソコンなどの端末のハッキングも行ないます。
最近は、スパイ機能のあるアプリが知らぬ間にダウンロードされているケースも増えています。
不特定多数の人物に対するストーカー行為だけでなく、知らぬ間に特定の人物の端末にスパイアプリを入れている場合も。
端末の挙動やバッテリーの持ちが急に悪くなった場合は、ハッキングの可能性も疑いましょう。
SNSアカウントのパスワードを特定して、アカウントを乗っ取られるケースも増えてきています。
少ない文字数の単純なパスワードだけでなく、名前や誕生日などから推測できてしまうパスワードも乗っ取りの危険性を増やします。
パスワードは当てずっぽうや推測で入力できない、複雑なものにしておきましょう。
今や、SNSに顔写真を公開することは、何も不自然な行動ではなくなりました。
しかし、自分の素顔を安易にネットに公開することでプライバシーが侵害される危険があります。
顔写真を真偽不明の情報とともに拡散された場合、嘘の風評が広まってしまうことが。
自分や他人を問わず、不必要に個人の顔写真を公開することは避けましょう。
ネットストーカー行為によって知り得た情報をもとに、現実のストーカー行為を実行する人もいます。
現実の犯行におよんだ場合は、ストーカー規制法などの法律によって対処が可能です。
立件するためには確実な証拠取りが必要なので、探偵に証拠集めを依頼するのがおすすめです。
根も葉もないデマや誹謗中傷を執拗に書き込むことも、ネットストーカー行為に該当します。
ネット上での書き込みは、開示請求を行なうことで発信者の特定が可能です。
スクリーンショットを集めておくだけでも証拠になりますので、確保しておきましょう。
ネットストーカー行為によって手に入れた情報を使って、脅迫行為におよぶ可能性も考えられます。
脅迫とネットストーカーの合わせ技は、ストーカー規制法違反と脅迫罪の両方に抵触する悪質な行為です。
毅然とした対応によって犯人に刑罰を与えることが可能なので、証拠集めはしっかり行いましょう。
特定の相手にメッセージやSNSのコメントを大量に書くことも、ネットストーカーの犯行の一つです。
その多くが好意やその裏返しとなる恨みが動機となり、内容は特に意味がなかったり時に誹謗中傷にまで発展することも。
SNSでは通報などでアカウントの凍結が可能ですが、何度も復活したりする場合は開示請求で犯人を特定しましょう。
ネットストーカーによる
ストーカー行為によって得た情報を使って、周辺人物まで特定されてしまうことも。
対象者を苦しめるため、家族・親戚・恋人・友人にまで嫌がらせを行なう加害者も中にはいます。
こうした場合、嫌がらせ被害の証拠収集を周囲に依頼しておくことで、犯人に対して訴えを出すことが容易になります。
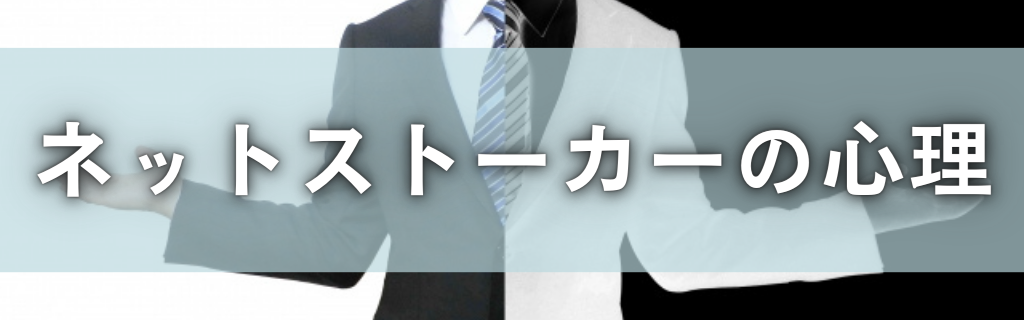
基本的に恋愛感情をもつ相手への誹謗中傷は、ターゲットの人が嫌がるような本人の写真を拡散投稿することはないかと思います。
ただし、振られたなどの恨みが伴う場合であればあり得るでしょう。
恋愛感情によりネットストーカーとなる場合、相手の個人情報を知りたい・住所を特定したいという一心で探偵を雇ったり、ウィルスを忍ばせるなど情報を入手すための行為を必死に行ないます。
入手後は、ネットストーカーが本格的なストーカーと化し、執拗につきまとい、違法と分かりながらストーカーを行ってしまう心理は世界中で起きています。
相手を所有したいというゲーム感覚・ゲームのヒロインを獲得する心理で、ネットストーカー行為に及ぶというのもあるかもしれません。
ターゲットとされた人のブログや動画を閲覧した人が書いてある内容や、ターゲットの容姿などに一方的に反感・憎悪・嫌悪感を抱くことからネットストーカーに発展するケースが頻発しています。
反感相手の個人情報を特定して晒したり、誹謗中傷を書くなど他の人がターゲットの不評感情を抱くように仕向けます。
同調圧力効果を意識して、ターゲットの人が多くの人から不評になることを狙うのです。
反感を抱いた人がネットストーカーになるのは、「あなたより自分の主張が正しい」「あなたの言っていることは間違っている」などと言われた際に頭がカッとなることが原因になりやすいのではないでしょうか。
また正義感で相手を正そうと意見投稿しているうちに、次第に怒りが沸騰してしまう人もストーカーになりやすいです。
この場合、お互いが正論ということで徐々に勝ち負けとなり、勝つまで相手を叩くという方向へネットストーカーはシフトしてしまいがちです。
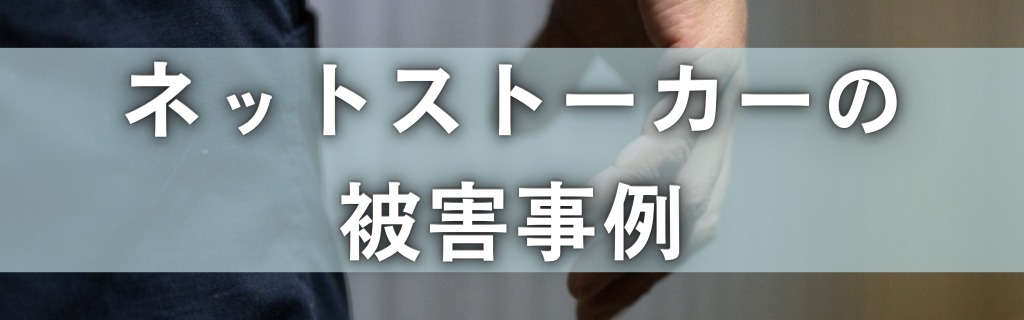
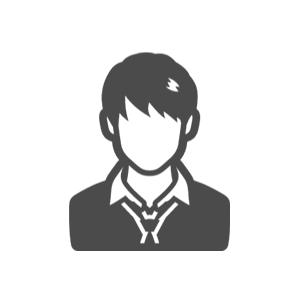
何となく政治に対して思うことをTwitterに投稿してみたら、自分と違う思想を持つ政治家の支持者に拡散されて批判のリプライがたくさん付きました。中には暴力を示唆する言葉や家族の特定を仄めかす言葉まで…。すべての書き込みのスクリーンショットを撮って訴える準備を整え、開示請求によって中傷を行なう人を特定できました。あのまま放置していたら身内にまで被害がおよんでいたかもしれないと考えると、今でも背中がゾワっとする感覚がします。
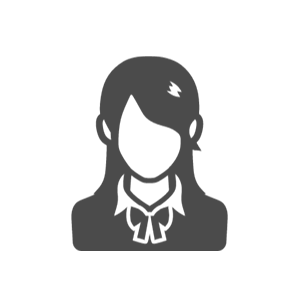
少し前からInstagramに多くのコメントを寄せてくれる人がいました。投稿した写真を褒めてくれるコメントがほとんどだったんですが、だんだん「大好きです」「付き合いたいです」という内容に変わっていきました。適当に流していたんですが、相手がどんどん本気になってきて、DMで長文のメッセージを送ってくるように…。もう我慢できなくなって「迷惑です」と伝えたところ、逆上したような怒りのこもったメッセージが立て続けに何通も送られてきました。怖くなってブロックしても、別のアカウントを作ってメッセージを送ってきて…。さすがに恐ろしいので開示請求を行なって本人を特定しました。被害に対して泣き寝入りしなくてよかったと思ってます。
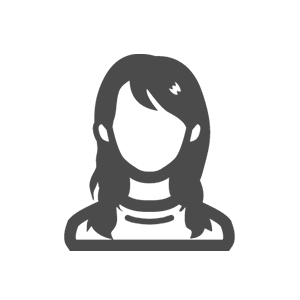
LINEで知らない人からのメッセージが送られてきて、最初はたまにはこんなこともあるかと思いましたが、日に日に違う人からのメッセージが増えていきました。その中の一人にどこで自分の連絡先を知ったのか聞いたら、掲示板サイトに自分のIDが晒されていることがわかりました。該当する掲示板の書き込みを特定して、開示請求をしたら最近は連絡がなかった知人の一人が私のIDをばらまいていたんです。その人とはもう縁を切りましたが、知人に個人情報を勝手にばらまかれたショックが大きかったです…。
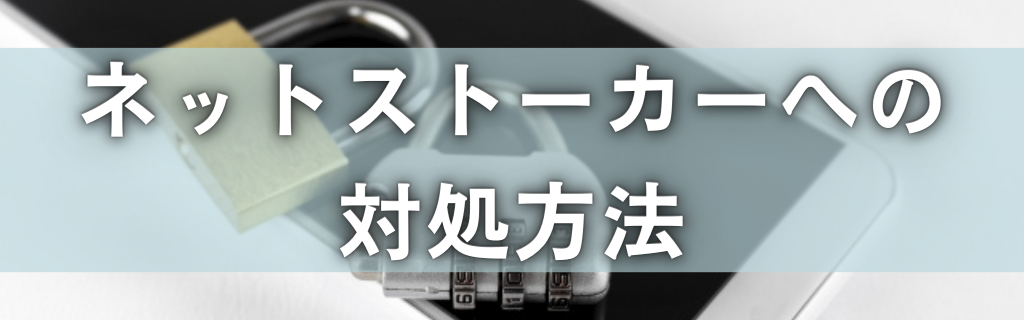
ブログや掲示板、グループラインなどに自分の考えを自由に述べることは良いことだと思うのですが、別の意見を持っている人からわざわざ反感を買わないように工夫してみましょう。
また自分の氏名やメールアドレス、写真は極力掲載しないように務めるというのも必要でしょう。
しかし、いくら自分の個人情報を掲載しないといっても、個人情報を盗む方法や聞き取りなどで入手することもできるため、すべての加害から自衛するのは困難です。
やはり、「情報を一切発信しない」ことがネットストーカーに巻き込まれるリスクを減らすことになるでしょう。
発信者情報開示請求によって、最近ではインターネットで他者を誹謗中傷する表現の発信者の情報を弁護士がプロパイダ等に開示の請求を求めることができるようになりました。
これを受けプロパイダ側は下記の情報を弁護士に開示する義務が生じます。
弁護士に依頼すると、発信者の個人情報を開示できるようになってきた近年の動きはいい兆候です。
弁護士に依頼するときは、あらかじめ相手と裁判をするという主体的な解決を求めていく姿勢の方にお勧めします。
しかし裁判をする以前に、「誰がどのような目的で行なわれているのか全貌を掴みたい」という方は探偵事務所に依頼しましょう。
ぜひ当事務所のネットストーカー調査をご検討ください。

探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。
しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑で困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、ネットストーカーの被害内容、ネットストーカーに関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口