みなさんはよくニュースなどで話題になる「いじめ」についてどれくらい知っていますか?
自殺率の増加や、SNSの普及による誹謗中傷の過激化が近年問題になっています。
さらに、子どもや学校だけでなく、会社や会ったことがない人と交流するオンライン上でも問題となってきています。
いじめを対策する法整備も進んではいますが、効果的とはいえない状況が続いているのが現状です。
弊社でも近年いじめや誹謗中傷に関する依頼が増えており、探偵が調査で入手した証拠が決め手となって、いじめ問題の解決に至っています。
いじめの現状について解説しつつ、止める方法や探偵を利用した解決策を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

一言に「いじめ」と言っても該当する行為にはたくさんの種類があります。
一般的に「いじめ」と思われる行為を上げていきたいと思います。
上記以外にも、たくさんのいじめの手口があります。
例えば、インターネット・SNSへの書き込み、金品を盗られる、家の壁などへの落書き、家にものを投げ込む等、上げればきりがありません。
そして、大人になればなるほど行為を隠したりエスカレートする可能性が高くなります。
いじめは加害者がちょっとした悪戯だと思っていても、被害者が精神的苦痛を感じたら「いじめ」です。
受けた側の気持ちに立った上で、もし自分が加担しないといけない状況になったとしても「NO」と言える勇気が大切です。
2013年に制定された「いじめ防止対策推進法」にて、いじめは下記のように定義されています。
「心理的、物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった人物が心身の苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は問わない」
「いじめの中に、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、被害者生命、身体または財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要」
上記のように「不快と感じた時点」でいじめと定めており、「いじめは犯罪である」ことを明確に記載しています。

いじめは、人が集団で生活している場所には必ず存在しているといっても過言ではないでしょう。
暴力や脅迫、仲間外れや無視など相手が嫌がることを直接行なうのに加えて、ネットを経由した「ネットいじめ」も広がっています。
■ネットいじめ
ネット上の掲示板やブログ、プロフィールサイト(プロフ)などで、匿名で特定の個人の誹謗中傷を書き込む、本人に無断で写真や名前・住所などの個人情報を掲載するなどの行為
その匿名性・陰湿性によって、加害者の特定や証拠の確保も困難になってきています。
ネット上では、文字でのコミュニケーションが主であり、ちょっとした感情の行き違いや勘違いにより誤解が生じてしまいます。
そして、集団感情の高ぶりにより、あっという間にいじめの標的にされることもあります。
また、現実社会での人間関係が投影されやすく、一度ターゲットとされるといじめが激化する傾向にあります。
現代人はネットが開かれた空間であるという認識が薄く、誰でも閲覧できるSNSや掲示板などを私的なやりとりやコミュニケーションに利用することも多いため、いじめが拡散するケースもあります。
年々増加傾向にあるネットいじめであっても、当事務所などの探偵・調査会社に依頼することで、被害の実態を調査できます。
弁護士とも連携し、IPアドレス開示や発信者情報開示請求によって加害者を特定し、被害届を提出し法定罰を受けさせたり損害賠償請求を可能とします。
また、探偵事務所や弁護士に調査を依頼していると相手に意識させることで、二次被害の防止にもつながります。
いじめ防止対策推進法とは、2013年6月28日に公布された法律です。
2011年に滋賀県大津市で起こった中学2年生いじめ事件が発端でこの法律が施行されました。
この事件により学校側、教育委員会側両者の隠蔽体質が浮き彫りになり、いじめ防止対策推進法が施行される流れとなりました。
この法律では上述したように「他の児童生徒が行なう心理的又は物理的な影響を与える行為」により「対象生徒が心身の苦痛を感じているもの」がいじめと定義されています。
つまり、「学校(義務教育)に通っている人が苦痛、嫌だと思う行為を定期的にされた場合はいじめ」ということになります。
まず、いじめ防止対策推進法では刑罰を与えるということは基本的にはありません。
学校側は、「いじめを受けた側」が安心して教室で過ごせるように「いじめた側」を別教室で授業を受けさせるなどの対応をします。
児童・生徒がけがをしたり長期間の欠席を余儀なくされるなどの被害が起きた場合には、学校が調査を行い事実関係を保護者らに伝えることを義務づけています。
いじめが起きた場合、学校はカウンセラーの協力を得ながらいじめを受けた児童・生徒を継続的に支援する義務などがあります。
実際に重大事件になった場合、いじめ防止対策推進法ではこのように定義されています。
つまり「必要に応じて停学処分、退学処分にします」ということです。
しかし、実際の判断は学校・教育委員会に任されるため、厳重な処罰を受けることは少ないとされています。
何より重大なのが、もしいじめの報告をしなくても学校側にも教員側にも罰則がないということです。
そのため、これはいじめではなく単なる喧嘩もしくはじゃれあいだと放置してしまい、重大化するケースがあります。
他にも自治体によって対応に差が生じる、調査などの決まりがないことが問題として挙げられています。
大人のいじめと子供のいじめでは対応が変わってきます。
まず、子供のいじめの場合は必ず大人が介入すべきです。
喧嘩をした場合は子供同士での話し合いは大事ですが、いじめに関しては違います。
いじめは結局いじめた側といじめられた側両方のケアが大事になってきます。
いじめた側も心に何かを抱えている可能性が高いです。
むしろ心に何かを抱えているのは「いじめた側」かもしれません。
きちんと大人が子供と向き合って話し合い、対策していくことが大切です。

自分や家族がいじめの被害者になってしまった場合、まず相手は誰でどんな目に遭わされたのかを証拠として集める必要があります。
これは相手に対して損害賠償請求を立てたり、警察への被害届の提出、刑事告訴など加害者を罰するために必要になります。
探偵事務所には「いじめた相手を訴えたいので、証拠を集めてほしい」という依頼のほかにも「子どもがいじめられているが加害者がわからない、特定してほしい」などの依頼が多くされています。
さらにLINEによるいじめなど、現代では暴力のような直接的でないいじめ行為の増加により問題が表面化しづらくはっきりした証拠が掴めないなど、解決方法が複雑になってきています。
公的にいじめを止めさせるには、下記の流れを踏みます。
「接近禁止命令」は男女間でトラブルが起きた場合、警察に相談すると近年はすぐに出される傾向にあります。
また開示請求をして内容証明を送った場合も、「次は逮捕です」という警告になるため、加害者がいじめを踏みとどまるきっかけになります。
ここまでできた場合は加害者を罰せなくても、警察からの任意での出頭や指紋採取、写真撮影が求められ犯罪者のような扱いを受けます。
(「接近禁止命令」はストーカー規制法の被害届が受理された場合、ネット上の匿名書き込み等は「開示請求」取得後の被害届が受理された場合)、また内容証明が弁護士事務所から郵送されてきた場合は家族にバレることになり、無視すると裁判で不利になります。
いずれも加害者にストレスとインパクトを与えることでいじめが止むことが多く、エスカレートした場合は被害者が有利になります。
また警察への任意出頭が行なわれると「前歴」が残るため、加害者の進路や就職に制限が付きます。
確かな証拠をつかんで動けば、多くの場合いじめは止まります。
探偵はいじめに関しては下記の証拠を集めることが可能です。
学校、会社など特定人物しか入れない場所でも、相手や周りにバレずに聞き込み・録音・録画が可能です。
また交友関係を調査することにより、いじめに加担した人物を特定することも可能です。
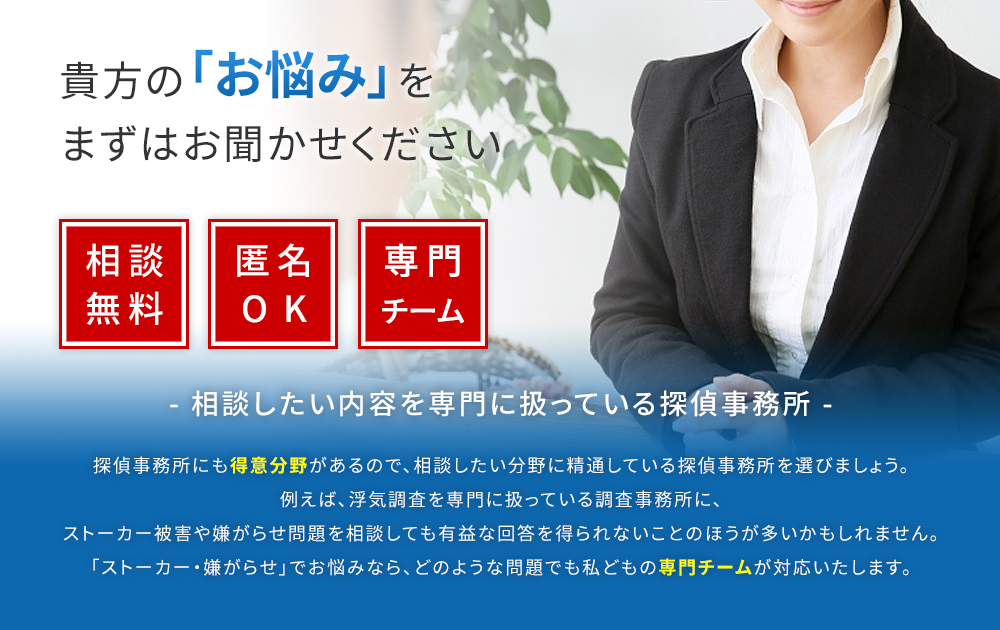
お住まいの場所や電車移動が不安・コロナウィルス対策で相談ルームまで行くのが不安な方のために、ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では出張相談を実施しております。
初めてのいじめに関するお悩みや不安などを、直接相談してみませんか?
各エリアの出張相談は、全て予約制で24時間、土日祝日もご予約を受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。
子供のいじめ相談先は、都内に住んでいる方は東京都いじめ相談ホットラインへ。
各道府県にお住まいの方は文部科学省の問い合わせセンターに問い合わせることをオススメします。
職場でのいじめの相談先は、各都道府県にある労働局や労働組合、もしくは会社内に窓口がある場合はそちらに相談しましょう。
それ以外の方は厚生労働省のこころの相談窓口やそのほかの相談サイトなどで問い合わせてみてください。
「いじめ」は一人で抱え込まないでまず相談です。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、被害の状況、対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口