ショルダーハッキングは、身体的接触や盗み見によってパスワードや個人情報を盗み出す手法です。
この記事では、ショルダーハッキングの仕組みや防止策について解説します。
個人の情報セキュリティを守るために知っておくべき重要な情報です。
ショルダーハッキングは、身体的な接触や盗み見によって個人の情報を盗み出す手法です。
例えば、パスワードや暗証番号を見られたり、クレジットカードの情報を盗み取られることがあります。
この手法は公共の場や混雑した場所で特に注意が必要です。パスワードや個人情報を守るためには、周囲の人に注意を払い、情報を隠す工夫が必要です。
また、セキュリティ意識を高め、情報の適切な管理を行うことも重要です。
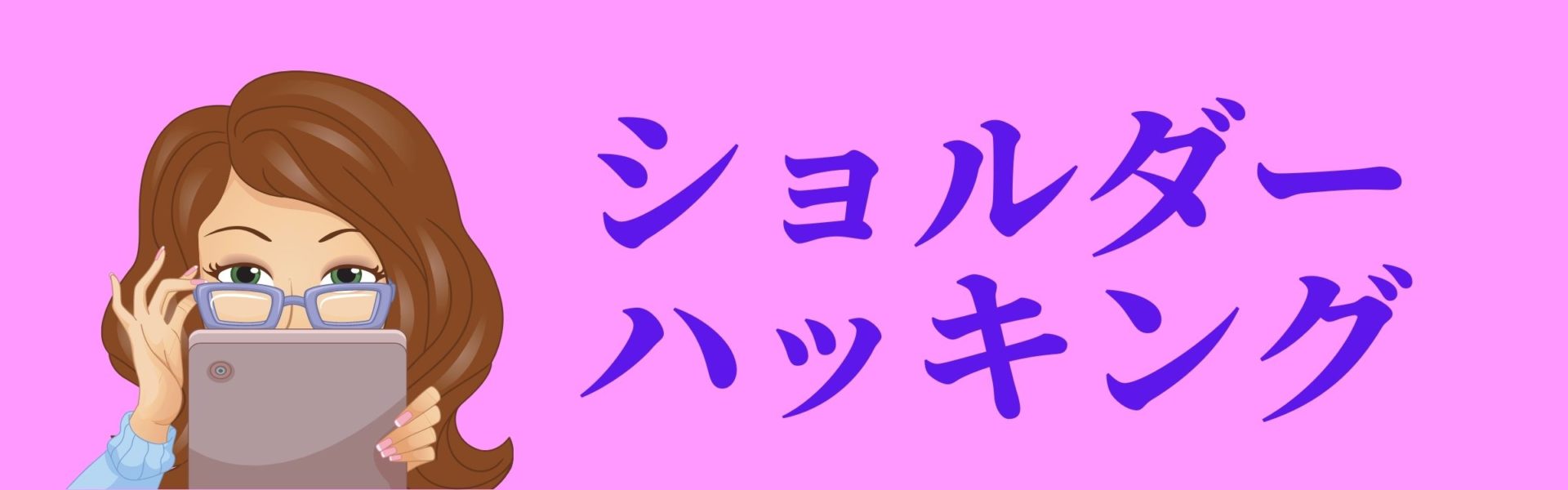
ショルダーハッキングは、以下のようなシチュエーションで発生する可能性があります。
これらのシチュエーションでは、自身の周囲に注意を払い、情報を隠すための対策を取る必要があります。
他人によるショルダーハッキングから身を守るためには、情報の取り扱いに慎重さとセキュリティ意識を持つことが重要です。
ショルダーハッキングは、その手口がアナログであるため、不正アクセスなどの痕跡が残らないことが特徴です。
ショルダーハッカーは、被害者が気付かないように巧妙に情報を盗み取り、痕跡を残さないようにします。
これは被害者が不審に思わずに情報漏洩が行われることが多いため、注意が必要です。
セキュリティ意識を高め、公共の場での情報取り扱いには十分な注意を払いましょう。
ショルダーハッキングは、狙いを定めた会社の社内システムにアクセスしなくても可能なため、悪意を持った、取引先などの出入り業者、宅配業者、郵便局員、清掃員などを装った第三者が潜入し、盗み取ることも可能です。
また、社員になりすまして電話でパスワードを聞き出すなどといったケースもあります。
加えて、取引先を装った問い合わせの電話で、機密情報を持っている社員を特定することもあります。
「ショルダーハッキング」に対抗するためには、人目につくところにはパスワードを書いた紙などを置かない、パスコードや暗証番号を入力するときには近くに人がいないかどうか確認するといったことが基本となります。
人によるアナログなハッキング手法であるため、対策も人への依存度が強くなるのが必然といえます。
まず、デジタルが普及した現代でも、現実として「ショルダーハッキング」という手口が存在することを情報を扱う個人が認識し、その取り扱いに注意するよう意識付けが必要でしょう。
Q
夫婦間でのLINEを盗み見する行為について
A
夫婦間で浮気などを心配して見る場合はプライバシー侵害の度合いが低いため、損害賠償は認められないか、認められても低い金額になります。盗み見たパスワードで、ロックを解除してログインした上でLINEを盗み見る行為は、不正アクセス行為となるため、罪が課せられる可能性があります。パスワードの設定がない場合に、勝手にLINEを盗み見る行為は不正アクセス禁止法違反にはあたりません。
Q
盗み見防止アプリとは?
A
スマートフォンの画面上にフィルムのような画像を表示し、正面以外の角度から画面を覗かれた際に、表示内容が見えない状態をつくるアプリです。電車やバスなど他人との距離が近い状態でスマートフォンを操作する際、画面内の情報が周囲の人の目に入ってしまう事を防止してくれます。短時間でも使えるため、画面に直接盗み見対策のシールを貼るよりも手軽です。
Q
ショルダーハッキングを避けるためにはどのような対策を取れば良いですか?
A
ショルダーハッキングを避けるためには、周囲の人に注意を払い、情報を隠すための対策を取ることが重要です。例えば、ATMやカード端末での取引時には、ボディシールドやハンドシールドを使用してPINコードや入力情報を隠すことが有効です。
Q
ショルダーハッキングが行われた場合、被害を防ぐために何をすべきですか?
A
ショルダーハッキングが行われた場合は、直ちに関係するパスワードや個人情報を変更することが重要です。また、信頼できる金融機関やサービスプロバイダーに連絡し、不正なアクセスや不審な取引を報告することも重要です。
Q
ショルダーハッキングから身を守るためにはどのような注意が必要ですか?
A
ショルダーハッキングから身を守るためには、公共の場や混雑した場所では特に注意が必要です。周囲の人に気を配り、スマートフォンやデバイスの画面を隠す、キーボード入力を遮るなどの対策を取ることが重要です。また、セキュリティソフトウェアやパスワード管理ツールの使用も推奨されます。
まず、現状について相談することから始めましょう。
ショルダーハッキングに関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口