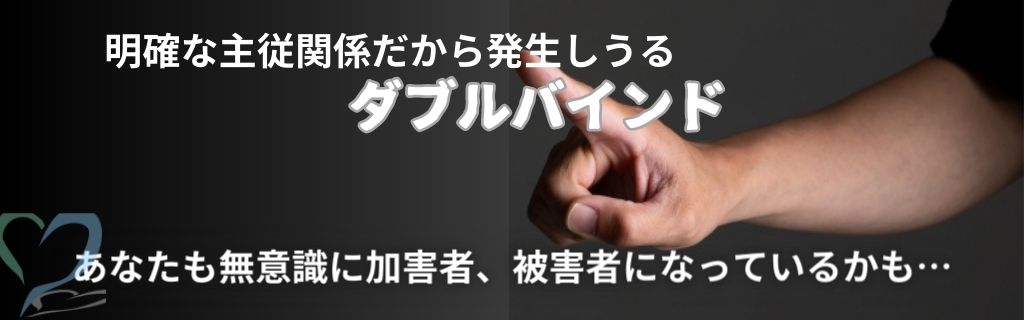
矛盾したメッセージを同時に発することで相手を追い込み、精神的に追い込むことを「ダブルバインド」と呼びます。
直訳すると「二重拘束」を意味し、米国の人類学者であったグレゴリー・ベイトソン氏が、統合失調症を研究する中で発見し、1956年に発表した論文において体系化されたものです。
例えば、仕事でミスをした部下に対して、その理由を述べさせたうえで「言い訳するな!」と怒鳴りつける上司…。
ビジネスシーンではよくある状況ですが、氏の理論の中では、このダブルバインドが繰り返されて心理的ストレスが蓄積されることで、精神疾患を発症するリスクが高まるとしています。
職場のみならず家庭やその他のさまざまな社会生活の中で起こり得るため、精神疾患の罹患や洗脳にも使われることもあります。
精神疾患の罹患や洗脳にも使われることもあり、無意識に委縮してしまい、主体性のない人間にされてしまうこともあります。
こうした「ダブルバインド」の主な事例から、被害者にもたらされるさまざまな悪影響、そして対処法に至るまで解説します。
ダブルバインドの分かりやすい事例として、子育てがあります。
例えば、子どもに「勉強しなさい」と言い付けておきながら、突然「お手伝いしなさい!」と命令すれば、子どもはどう行動すればいいのか混乱します。
その2つの命令を同時にこなすことは不可能だからです。
特に親子の主従関係は明確であり、コミュニケーションが一方的であることも多く、こうしたできごとが日常的に行なわれてしまいます。
ダブルバインドは徐々に子どもの精神状態をむしばみ、結果として具体的な指示がなければ何もできない指示待ち人間に育ってしまうことも。
深刻なケースでは、自己肯定感のない人間になったり、自分一人では何も決断できない発達障害を発症することもあります。
これは大人に関しても同様で、上司からのダブルバインドに苦しみ、自分を責めた挙げ句に精神を病むケースも後を絶ちません。
前出のベイトソン氏は「ダブルバインド」とは、次の6つの条件がそろった際に成立すると定義しています。
ベイトソン氏の仮設では、これらの条件が揃えば、どんな人間でも判断能力に悪影響を及ぼすとしています。
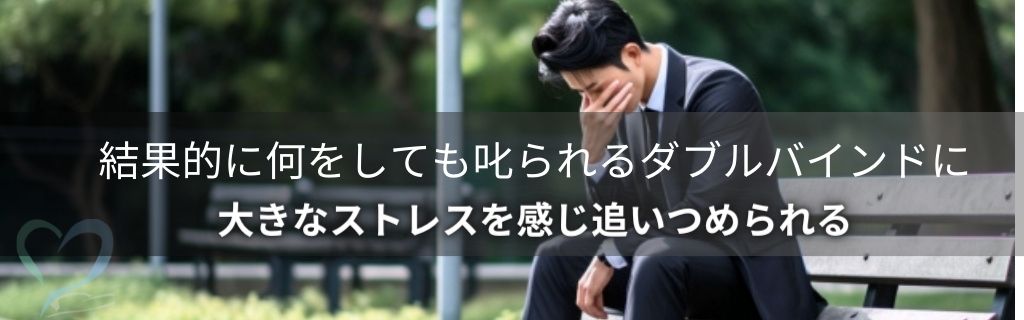
職場などでは上司と部下の間など、強制力のある形で理不尽な命令や脅迫などの「ダブルバインド」が見られます。
その他の場でも、何らかの力関係の上下がある所で発生することがあります。
つまり、日常的なやり取りの中でも起こり得るという意味です。
特に日本社会では空気を読むことを重要視し、組織風土の常識に染まることが良しとされる傾向にあり、ときとして、組織風土が世の中の常識や法律をも超越することさえあります。
その結果、悪意などとは無関係に立場的に有利な者が無意識のうちに周囲の人物を苦しめることにもなり得るのです。
暴力以外の言葉などで精神的ダメージを与えるハラスメント行為である「モラル・ハラスメント(モラハラ)」に、「ダブルバインド」の手法が併用されるケースも多く存在します。
上司に指示を仰ぐ時、上司が「いちいち聞いてくるな」と言っていたにも関わらず、自分で考えて仕事を進めた結果「相談もせず勝手に進めるな!」と怒鳴られたとしましょう。
そうなると、部下は次からどのように仕事を進めればいいかわからなくなってしまいます。
このような理不尽なコミュニケーションは部下に不必要なストレスを与える上に、組織全体ひいては日本経済全体として、労働生産力の低下を招いているといっても過言ではないでしょう。
洗脳する人は、人の弱さに付け込むことに長けています。
よって、自分のことを自分で決められない人の心の隙に入り込むことも得意です。
心を病みつつある人は、自責の念が強い上に相手の言い分を簡単に受け入れてしまうため、洗脳しやすい状態ともいえます。
例えば「できないのなら言う通りにやれ!」と言われた結果「自分はできない人間なんだから、言う通りにしよう」と思い込んでしまい、洗脳状態になっていく危険性があります。
「ダブルバインド」は職場のみならず、家族間でも起こりやすいです。
精神的な暴力は身体的暴力よりもわかりにくいため、それがモラハラかどうか気づきにくい側面があります。
特に家庭内での密室において、さまざまな矛盾に悩んだ結果、精神的に混乱して思考力が損なわれていきます。
そして、その環境下で生きるために加害者に逆らえなくなったり、自分を抑え込むことで相手の言いなりとなる洗脳状態となることも。
なおかつ、統合失調症や発達障害、鬱病などの精神疾患に罹患する可能性も高まります。
長期的なダブルバインドに伴う精神的なストレスによって、被害者側は「また怒られるのでは…」という恐怖から自分の判断や行動が全て間違っているのではないかと考え、自信も喪失していきます。
また必要以上に相手の顔色を伺うようになるので、自己肯定感や主体性も失われてしまいます。
さらに、何を信じていいかわからなくなるためコミュニケーションも構築しにくくなってしまい、重症になると適応障害を罹患することも。
パワハラやモラハラがまかり通っている職場は、精神的に病んだ従業員ばかりとなるブラック企業となり、当然ながら恐怖で支配される職場に生産性の向上など期待できません。
問題となっている悪徳新興宗教の霊感商法においても、このダブルバインドの手法が悪用されています。
「寄付か物品購入による神からの加護」か「地獄に落ちるか」の二択を迫ることで、信者を取り込んでいます。
そこに「逃げる」「その場から離れる」という選択肢を与えないことで、被害を大きくしています。
この手法は、新興宗教に限らず、さまざまな形の悪徳商法にも使われています。
おかしいと思いながらも相手の話を聞き、同意してしまいがちな人は思わぬ形でカモにされる危険性もあります。
ダブルバインドの状態が続くと、ストレスによる精神的なダメージから、統合失調症などの精神疾患に罹患することもあります。
その予兆として「感情を抑え込むようになる」「自信が持てなくなる」「自由な意思決定ができなくなる」「心身に不調をきたす」などの症状がみられます。
真面目で周囲に気を遣う人ほどストレスを感じやすく、自己否定が強くなると鬱病や対人不安などを引き起こすこともあるでしょう。
職場において、上司が部下に対してダブルバインドを戦略的に使っている場合は対応がやっかいです。
矛盾した異なる指示を与え、思考停止に陥らせて判断力を奪うことを嫌がらせや上司自身の優越感のために使うモラハラも存在します。
そのような職場であれば、上司に闘いを挑むよりも、逃げることを選ぶことを優先するべきでしょう。
さらに上の上司に相談することもできますが、個人でダブルバインドされている証拠を取ることは困難です。
憔悴してメンタルを病んでいる状態で立ち向かっていくより、部署異動や転職を視野に入れた方が安定した気持ちを保つことができます。
精神状態を崩さないために、ダブルバインドというハラスメントがあることを知って、いち早く気づけるようにしておくことも重要です。
ダブルバインドを受けると「できなかった自分が悪い」と言う自責思考に囚われがちですが、客観的に見れば自分だけが傷ついている構図に気づくでしょう。
「自分が悪い」と言い聞かせて相手を責める気持ちを抑えがちですが、自分をいたわって気持ちを回復させて自分の感情を優先させた行動を起こすことも、精神状態を回復させるために重要です。
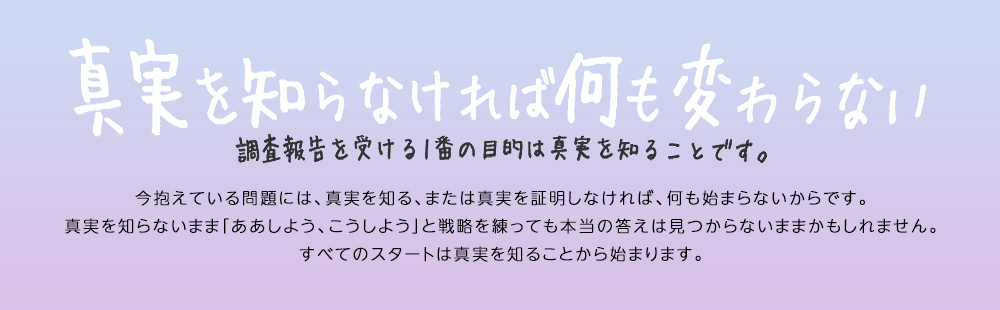
ダブルバインドされている側は、被害を受けていることに気付きにくい上に、声を上げにくい現実があります。
しかし、ダブルバインドされていることに気づいた瞬間から対処を行なう必要があります。
ダブルバインドを用いるようなパワハラ上司は、他の部下に対しても同じようなことをしていると思われます。
しかも、反抗してこないような人物を選んでパワハラ行為をしてくるような狡猾な手口を用いています。
自分一人で対抗するには証拠を掴むことが重要です。
例えば、ICレコーダーでダブルバインドを用いたモラハラやパワハラを受けた時の録音を残しておくといいでしょう。
それでも解決が難しく、訴訟問題に発展しそうなほどのトラブルに巻き込まれたときは、パワハラやモラハラ行為の証拠収集の専門家にご相談ください。
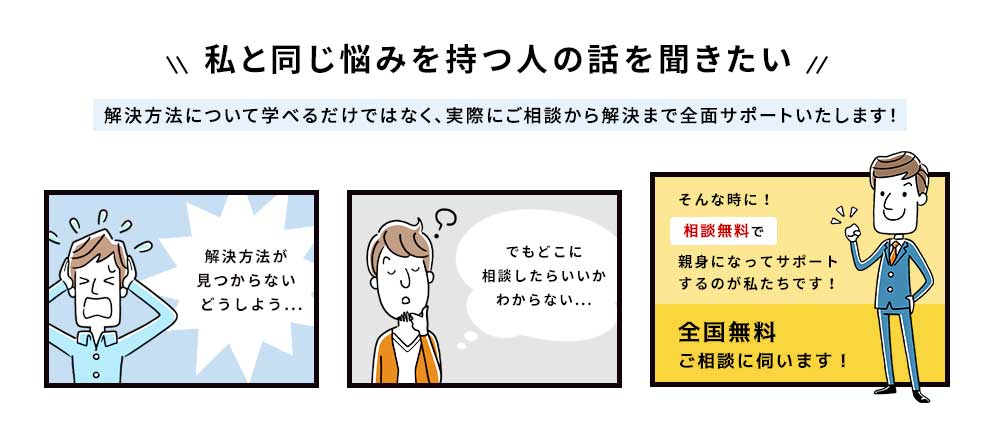
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口