
「アルハラ」とは、職場の飲み会の場などで行われるハラスメントを指す「アルコール・ハラスメント」の略称です。
お酒に弱い人に対して無理やり飲酒を強要したり一気飲みさせる行為は、最悪の場合急性アルコール中毒などによって死に至る行為です。
当然ながら強要した人はもちろん、その場にいた人もが罰を受ける可能性があります。
職場にて飲み会を通じて親睦を深めることは「飲みニケーション」と呼ばれますが、若者のアルコール離れが進み、現在では飲酒習慣のある20~30歳代男性は3割程度です。
体質的にアルコールを受け付けない「下戸(げこ)」の人も増えています。
加えて、お酒は飲めるものの、肉体的・精神的健康などのためにあえて飲まない「ソーバーキュリアス」と呼ばれる若者が、およそ半数にも上っています。
一方、若者の「飲み会離れ」が進んでいるのかといえば必ずしもそうでもなく、飲み会や職場内イベントへの参加志向は6割を超えている調査結果もあります。
あくまでも「飲みニケーション」から離れているだけで、職場におけるコミュニケーションから離れているわけではありません。
そんな中、職場の飲み会において、アルコール慣れしていない若い社員や女性社員に飲酒を強要する「アルハラ」事案が起きています。
ここでは、「アルハラ」の定義や事例、アルハラ被害に遭った時の対処法やどのような犯罪に問えるのかなどを解説します。
アルコールハラスメントは、お酒を飲むことを強要したり飲ませるような雰囲気を作り出す行為を指します。
「お酒の席だから…」「酔っていて覚えていない…」。この国ではよく聞く言葉であり、「逃げ口上」として許されている空気さえあります。
まさにこの悪しき風習が「酒席においては何をしても良い」という間違った常識を作り出しているといえます。
アルコールの強要により家族や子どもを亡くした遺族を中心とした「イッキ飲み防止連絡協議会」では、以下の5項目をアルハラ行為と定義しています。
アルハラが起きやすいシチュエーションとして、まず挙がるのが大学生による新入生歓迎会です。
新入生は未成年であることも多く、未成年に飲酒させる時点で違法行為です。
その上、飲み会コールや上下関係を持ち出して、無理やり慣れない飲酒をさせることで急性アルコール中毒を引き起こすリスクが高くなります。
急性アルコール中毒によって死に至るケースは多く、後遺症が残ることもある深刻な病気です。
辛うじて急性アルコール中毒を免れたとしても、大量の飲酒による酔いは遅れて体を襲い、帰り道や帰宅後に急激な体調不調をきたすこともあります。
一人暮らしの自宅で潰れてしまい、吐いたものがのどに詰まって窒息死してしまう危険性も。
また、若くしてそのような経験をしたことでお酒嫌いになったり、職場の同僚や友人との酒席そのものを忌避する不幸なトラウマを背負うケースもあります。
仕事上重要な取引先や関係先との酒席の場合、特に相手との上下関係が明確な場合、相手からの酒の勧めは断りにくい現実があります。
中でも、中高年の間には未だに「酒嫌いは飲めば治る」「お酒を飲めないなんて社会人失格」などの旧時代的な理屈で飲酒を強要するケースもあります。
このような事態を乗り切るために、「明日早くから車を運転する」「医者からお酒を止められている」といった方便を駆使して、角が立たない程度に断るのも知恵の一つといえます。
職場の飲み会における、下記のような行為はれっきとした人権侵害です。
業務外の出来事とはいえ、職場での立場の違いを悪用したハラスメント行為・犯罪行為ともいえるでしょう。
「飲酒によって人間関係が重要」「上下関係に厳しい」などといった社内風土は悪しき風習であり、従う必要など全くありません。
それによって嫌な思いをしたり、人間関係に悪影響を及ぼしたなどの被害を感じたら、社内のハラスメント窓口に相談するか法的手段を取ることも検討しましょう。
一気飲みをさせて急性アルコール中毒となってしまった場合、一気飲みをさせた人物だけでなくそうした雰囲気を作った人物も含めて「傷害罪」に該当します。
傷害罪とは、一般的に「相手にケガを負わせた場合の罪」に限ったものではなく、精神的苦痛を与えて精神疾患を負わせた場合などでも該当します。
傷害罪が成立すると、15年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられます。
また、被害者が死に至った場合「傷害致死罪」にあたります。
「傷害致死罪」の法定刑に罰金刑は存在せず、3年以上の懲役となるため罪がより重いといえるでしょう。
他にも、刑法では一気飲みを止めなかった者やあおった者も「傷害罪の共犯」や「傷害現場助勢罪」が成立し得ます。
傷害罪の共犯が成立すれば、正犯と同じよう罰に処せられることもあります。
また、傷害現場助勢罪が成立すれば1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。
一気飲みをせざるを得ない状況を作り出した人物や、それを傍観していた者も罪に問われる可能性があるため注意しましょう。
アルハラによって死に至らしめた場合、「過失致死罪」に問われる可能性もあります。
これは、死亡させる意図がない過失の状態で死亡させてしまったと判断された場合に成立するもので、50万円以下の罰金に処せられます。
傷害致死罪と比べれば罪が軽いようにも感じますが、これはあくまで誰が見ても過失であった場合に限ります。
全員が一気飲みに参加していた、罰ゲームで一気飲みをしていたなど、明らかな意図があったとみられる場合には過失致死罪にとどまる可能性は低いといえるでしょう。
2012年、学生サークルの飲み会にて当時21歳の学生が急性アルコール中毒で死亡しました。
飲んだお酒はアルコール度数25%の焼酎原液で、それを1リットル以上も飲ませた結果起きた悲惨な事故です。
この事故では、酔い潰れた学生を周囲が4時間も放置し、救急車到着の2時間前には死亡していました。
その場に同席していた学生は救急車が到着したと同時に逃げたとされ、「保護責任者遺棄致死罪」に問われました。
その後、謝罪した10人とは1人240万円の支払いで和解が成立したものの、責任を認めず和解に応じなかった残る21人に対し、総額1億6900万円の損害賠償を求めて提訴しています。
アルハラ行為による提訴には、民事責任と刑事責任の両面が考えられます。
まず民事責任の場合、相手が自分の意思に反して飲酒を強要して精神的な苦痛を与えたことによる「不法行為責任」で訴えることが可能です。
これは飲酒をはやし立てたり、飲酒によって気分が悪くなったときに救護を行わなかった人も対象です。
加えて、飲み会での不法行為責任が認められた場合、職場の飲み会であれば企業側にも使用者責任が発生し、損害賠償請求が可能となります。
そして、アルハラ行為における刑事責任として、下記の刑罰が科されます。
加えて、無理のお酒を飲せる行為については「強要罪」も適用されます。
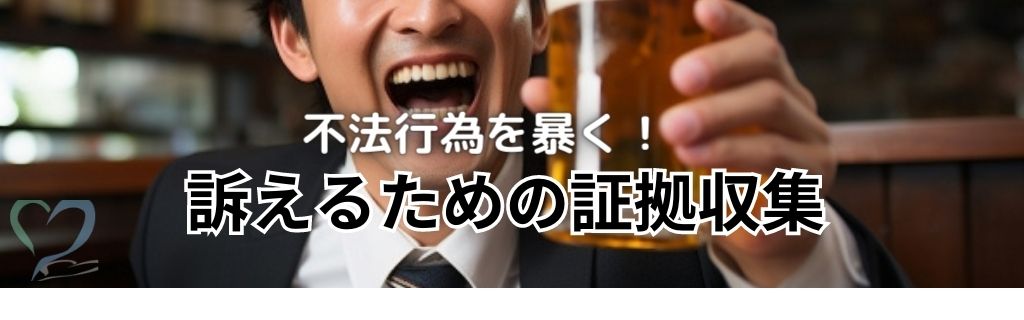
アルハラに関連して、さまざまな不法行為が付随している場合が多く存在します。
まずは、セクハラとして女性参加者の体を触る、卑猥な発言をする・させる、お酌を強要するなどが当てはまります。
これらの行為は不法行為責任による損害賠償請求ができるほか、強要罪や強制わいせつ罪に問うことも可能です。
そして、上司や先輩がその立場を利用して人格否定にも値する暴言を吐いたり、暴力を振るってきた場合はパワハラに該当します。
こちらも損害賠償を求めることが可能な上、暴行罪・傷害罪・名誉毀損罪・侮辱罪などで訴えることもできます。
民事訴訟の場合、金額損害賠償140万円を超える訴訟は地方裁判所で扱うことになります(140万円以下の損害賠償請求が簡易裁判所)。
その場合、下記のものが証拠として扱われます。
ですが、アルハラによる刑事告訴については、「飲酒を強要された」程度では被害届が受理されにくいのが現実です。
例えば、酒席において一気飲みを強要され救急搬送された、酔い潰れたまま放置された、体を触られるなどのわいせつ行為をされたなどであれば、被害届が受理される可能性が高いです。
飲み会において不穏な空気があれば録音しておくのも、後々自分の身を守る貴重な証拠となり得ます。
アルハラは、お酒を受け付けない体質の人にとっては、時には命を落とすこともある事案です。
アルハラ被害に遭わないためにはお酒の席に参加しないことが何よりの予防策となりますが、あまり現実的ではありません。
当事務所ではそうした方のために、ご依頼があれば酒席の場に駆け付け、飲酒の強要などのアルハラ行為などがあれば写真や動画を撮影し、証拠を確保した上で後の損害賠償請求などを有利に進めるお手伝いをいたします。
一気飲みの強要などを撲滅するべく、「特定非営利活動法人ASK」が、以下のような相談窓口を用意しています。
それでもアルハラ被害に遭い、加害者との平和的解決が難しく訴訟問題に発展しそうなほどのトラブルに巻き込まれたときは、ハラスメント証拠収集の専門家にご相談ください。
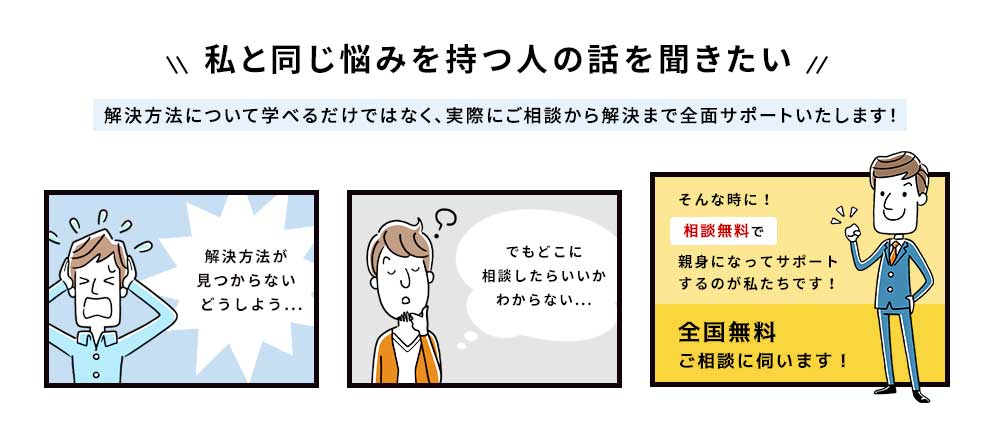
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口