「いじめ」とひと口にいっても、その行為はさまざまです。
しかしながら、その多くが犯罪に類するものといっても過言ではありません。
加えて、一昔前まではいじめが学校で起きるものと言われてきましたが、近年では会社や職場における「大人のいじめ」も問題視されています。
時としていじめを苦に自殺してしまう事件が起こるなど、いじめは人生を大きく狂わせます。
この記事では、いじめ行為が該当する犯罪や、いじめの解決方法について解説します。
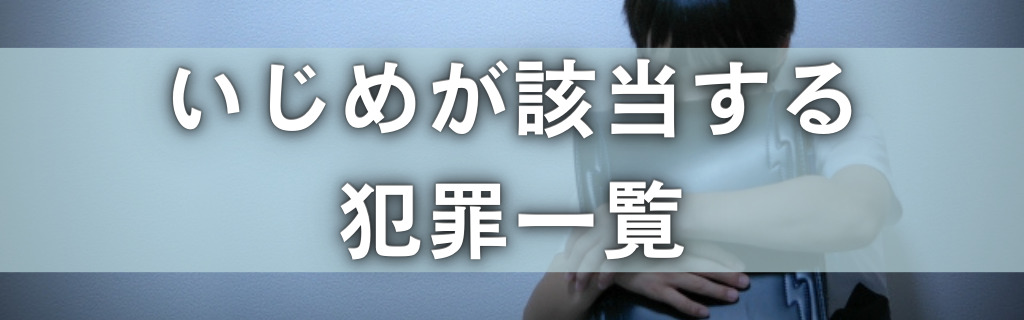
「いじめ」とされている行為の多くは、内容をよく見ると犯罪行為に該当する場合があります。
犯罪行為に対して「いじめ」という言葉を使うのは、事態の矮小化につながりかねません。
実態を把握するためにも、いじめ行為に該当する犯罪を知っておきましょう。
強要罪は、他人の身体・財産・自由・名誉に危害を加えることの告知または暴力によって、義務にない行為を行なわせたり権利の行使を妨害した際に科せられる罪です。
刑法223条では、懲役3年以下の罰則が規定されています。
例えば、恥ずかしい秘密の暴露をほのめかして無理矢理何かをさせるといった行為は、強要罪に該当します。
子どもの間でも精神的な圧力や暴力による強要は起きる可能性がありますので、注意しましょう。
器物損壊罪は、他人の所有物を壊した際に科せられる罪です。
刑法261条では、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が規定されています。
他人の物を壊すことは、いつどこでも起きる可能性が考えられます。
持ち物を守る対策を取るだけでなく、身内を加害者にしないための対策も必要です。
傷害罪は人の身体に傷害を与えた際に科せられる罪で、暴行罪は人を暴行した際に科せられる罪です。
一見同じような内容に見えますが、人にけがをさせたかどうかで判断が分かれます。
基準
罰則
比較すると、暴行罪の方が罰則規定が軽いです。
もしけがを伴う被害があれば、傷害罪として扱う方向で進めましょう。
恐喝罪と強盗罪は、ともに暴力や脅迫によって金銭や財産を奪う行為への罪です。
違いとしては、暴行や脅迫が相手の反抗を抑圧するのに足りるかどうかにあります。
例えば「お金をやらないと痛い目にあうから渡そう」と思わせた場合、反抗の余地が残されているとして恐喝罪になります。
反対に、反抗の余地が残らないほどに暴力や脅迫を行なって金銭を奪った場合は強盗罪です。
罰則は恐喝罪が10年以下の懲役、強盗罪が5年以上の有期懲役と強盗罪の方が重いです。
子どものいじめでも、身体の自由を奪ってものやお金を奪うことは強盗罪と同じ。
対策として、必要以上のお金や持ち物は持たせないようにしましょう。
窃盗罪は勝手に他人の占有物を盗った際に科せられる罪で、横領罪は人から預かっているものを自分のものにしたときに科せられる罪です。
違いとしては、持ち物を勝手に盗ったか預かったものを自分のものにしたかにあります。
子どものいじめでも、本やゲーム機など貸していたものを返してもらえない場合は横領罪。
持ち物を勝手に奪われた場合は窃盗罪です。
刑罰は窃盗罪が10年以下の懲役または50万円以下の罰金、横領罪は5年以下の懲役になります。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫によって被害者の意思に反してわいせつな行為を行なうことへの罪です。
体への接触・キス・脱衣など性欲を刺激し興奮させる行為
中には性的好奇心が高い子どももいるため、そうした子どもが先鋭化した行動を取る可能性もあります。
刑法176条では、強制わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役が罰則です。
もし強制性交にまでおよんだ場合は、5年以上の有期懲役にまで重くなります。
子どもの変化には目を配り、何が起きているかいち早く把握できるようにしましょう。
名誉毀損罪は事実を公言して人の名誉を傷つける行為に科せられる罪。
侮辱罪は具体的な事実ではないことで人を侮辱した際に科せられる罪です。
両者の違いは、内容が事実かどうかにあります。
名誉毀損罪は、内容が事実であっても名誉を傷つけたと判断される行為に適用されます。
侮辱罪は、「バカ」「アホ」など単純な悪口や事実でない内容による相手の侮辱が該当します。
刑罰は名誉毀損罪が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金。
侮辱罪が1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは三十万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
子ども同士の口喧嘩でも名誉毀損・侮辱に発展するケースは大いにありますので、深刻な場合はボイスレコーダーを持たせるなどの対策をしましょう。
上記以外にも、犯罪にならずとも立派ないじめ行為はいくつもあります。
これらの行為は特定の犯罪には当てはまりにくいため、罰則を問えないでしょう。
しかし、民事上の責任を問える可能性はあります。
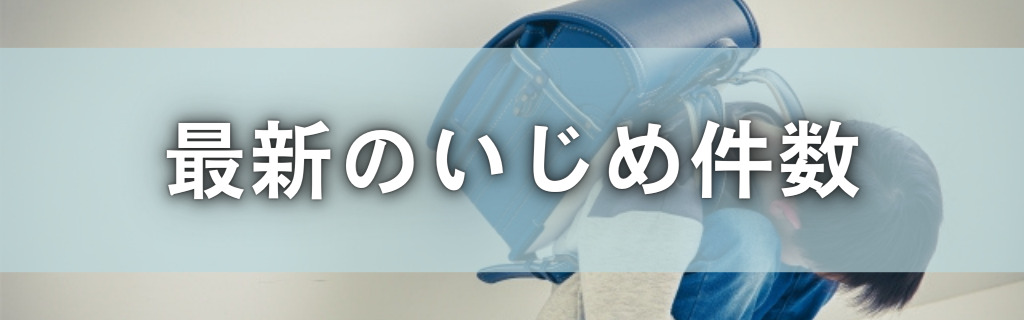
現在、日本国内のいじめ事情はどうなっているのでしょうか。
いじめの件数だけでなく、子どもを守る学校側の対応にも注目する必要があります。
もちろん各学校によって対応はケースバイケースですが、一つの参考値として確認しておきましょう。
令和3年に文部科学省がまとめたデータから、全国小中高におけるいじめの認知件数を読み解いていきましょう。
大多数のいじめは小学校で報告されており、実に全体の7割以上に上ります。
しかし、思春期を迎えて思考が成熟する中で、色々なことを気にして被害を公表しない子どもも増えていきます。
そのため、実際に起きているいじめはこの数字よりもずっと多い可能性も考えられます。
総務省の調べによると、いじめを発見するのは学校職員が最も多く、全体の66%に上ります。
他には、教職員以外からの情報が34%、本人からの訴えが18.1%です。
数字で見ると、まだまだ被害者本人から声を上げにくい現状であることが伺えます。
学校内だけでなく、家庭内でも子どもが声を上げやすい環境作りが重要です。
令和3年の文部科学省調べでは、認知されたいじめの内、警察への相談・通報に至ったのは1,334件と全体の0.2%しかありません。
また、加害者側の子どもにはスクールカウンセラーや警察・児童相談所・病院などの対応が行なわれていますが、それも全体の2.3%しかありません。
被害者の子どもにも同様にスクールカウンセラーや児童相談所が対応していますが、これも全体の2.8%しかありません。
被害者・加害者の子どもには、個別のケアが行き届いていないのが現状といえるでしょう。

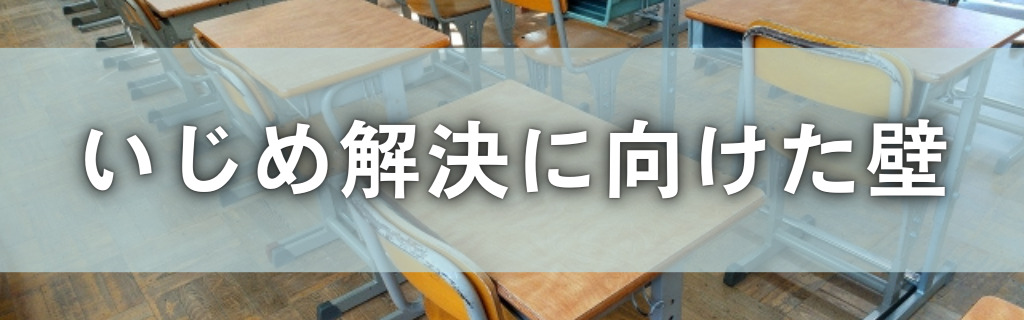
いじめがここまで根深い問題となっているのに、なぜ未だに根本的な解決に至らないのでしょうか。
それは、いじめ行為の特性や学校という現場の特殊性が関係している部分もあります。
いじめの解決に向けて壁となっている要素を知っておきましょう。
いじめ行為が、大人の目に入る場所で公然と行なわれることはほぼないでしょう。
加害者となる子どもも、大人の目がないため自制心が働かずに犯行に至る場合も考えられます。
しかし、場合によって大人がいない隙を狙って意図的にいじめ行為に及ぶ場合も。
いずれにしても、教職員以外の大人がいじめの決定的瞬間を見つけるのは難しいといえます。
いじめの認識については、被害者と加害者側で認識が異なることがあります。
被害者側がいじめだと感じた行為も、加害者側がそのつもりがないという認識なら被害は一気に矮小化してしまいます。
いじめを「子ども同士の悪ふざけの延長線」と捉える大人も多いため、いじめ問題がなかなか深刻化しない要因といえるでしょう。
学校は、在籍する子どもや教職員以外の出入りは侵入者防止の観点からできない決まりです。
しかし、それが学校特有の閉鎖性を生んでしまう一因ともいえます。
学校内で起きた問題に関しては、基本的に教職員が対応することが世間一般の認識です。
もし学校内で対応できない深刻な問題が発生した場合、対応できなかった責任は学校長などの上層部に向けられます。
もし上層部が自分の進退を気にしてしまえば、いじめが隠蔽されたままになる可能性もあります。
そうなれば、刑法で刑罰の対象になる行為も表ざたにならずに終わってしまうことも。
結果として「治外法権」化してしまっている学校という場所の閉鎖性が、いじめの解決を遅らせている一面があるといえるでしょう。
上述したように、外部の人間は学校に入れないため、証拠集めに動くことは難しい部分があります。
下手に侵入すれば建造物侵入罪に問われてしまうため、いじめの特定には被害者自身および周囲の人たちの協力が何よりも欠かせません。
そのため、通常の事件よりも発見が遅れてしまうことが挙げられます。
いじめの解決に向けて、家族も含めた外部の人間ができることは限られてしまうのが実情です。
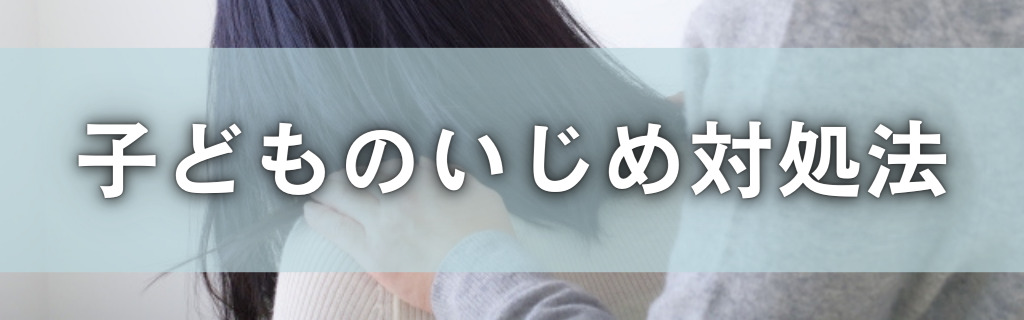
もし自分の子どもがいじめを受けているとわかった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
協力を仰ぐべき存在や、親御さんができることも併せて解説していきます。
まず最初に理解しておきたいのは、子どもにとっては学校が一つの社会になっています。
そのため、学校で起きたことはまるで一生に関わる一大事かのように認識してしまう部分があります。
しかし、世界は学校だけではないことを大人は知っています。
学校の外にも居場所があるということを、子どもに認識してもらうように動いてみましょう。
校外活動に積極的に参加させてみたり、学校に行きたくない日は行かせない選択を取るのも重要です。
大事なのは、最悪の事態だけは回避すること。
学校以外にも生きる道はあるという認識を、子どもに意識させてみましょう。
学校で一番子どもに近い大人は、やはり教員になります。
教員の方が、家では見せない子どものリアルな一面を把握しているものです。
もし家でもわかる変化が起きたら、学校でも何か変わったことがないか相談してみましょう。
教員もより意識して子どもを見てくれるようになり、ささいな変化を汲み取れるようになるかもしれません。
もし既に危害が出てしまっている場合は、警察に相談するのも手です。
告訴状や被害届を提出することで、深刻な事態が起きていると学校や関係者に認識させることができます。
いじめを立証するための証拠集めが難しい場合、探偵に調査を依頼するのも手です。
探偵は証拠集めのプロであるため、学校内に入ることはできませんが、聞き込み・張り込み・尾行を駆使して有力な証拠を掴みます。
もし裁判になったとしても、証拠として提出できる報告書を作成可能です。
相談は無料で行なっており、受付はメール・電話・LINEで24時間365日対応します。
今現在いじめ被害にお悩みの方は、ぜひ当探偵事務所にまでご相談ください。
Q
最近息子の元気が無く、ご飯も食べない様になりました。いじめられているのか聞いても答えてくれません。どうしたらいいのでしょうか?
A
子供の現状を把握して対策してあげましょう子供が元気なく帰ってくるのが頻繁になったら親なら誰しも心配になるでしょう。親が知ったからと言って必ずしも解決する訳ではないですし、親が何か行動を起こしていじめがエスカレートする事も考えられます。よって我々専門家が第三者として客観的に状況を見ていじめの現状、いじめを行っている子共を特定する事が出来ます。 我々が出来る事と致しましては「張り込み」「聞込み」や状況に応じてインターネット「ネットリサーチ調査」が中心となります。また、子どもからの情報提供など、子どもができる範囲で調査の協力をお願いする場合があります。現状によって出来る調査も異なるのでまずは我々専門家にご相談ください。
Q
娘がSNS上でなりすまされてから学校でいじめを受けている様です。何か対策はあるでしょうか?
A
ネットリサーチ調査でなりすました人物を特定しましょう現在の学生位の年代であるとSNSは誰しも使っているツールだと言っても過言ではないでしょう。この場合は、「ネットリサーチ調査」で偽アカウントを突き止めて削除と成りすましの人物の特定しましょう。また、なりすました人物を特定してもいじめは続く可能性が十分に考えられる為、親、専門家のアフターフォローが重要になるでしょう。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、いじめに関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口