現在、すっかり「ブラック企業」という言葉が定着しています。
意味としては、「違法な長時間・過重労働・違法労働・パワーハラスメントを課す企業」を指す言葉です。
低賃金・劣悪な環境で厳しい労働を強いるブラック企業の存在によって、企業間の健全な競争が損なわれ、結果として日本企業の国際競争力や生産性の低下をもたらしています。
また、ブラック企業の経営者や経営幹部に「コンプライアンス(法令遵守)」の意識は皆無である場合がほとんどです。
こうした不正企業の姿勢を追及して改めさせる、あるいは市場からの退場を求めようにも、一人では不安もあります。
さっさとと転職するのも一つの手ですが、社員を一人失ったくらいで企業が考えを改めることなど期待できません。
もしブラック企業の誤った経営姿勢を改めたいと考えたときに、どう行動を起こすべきなのか解説します。
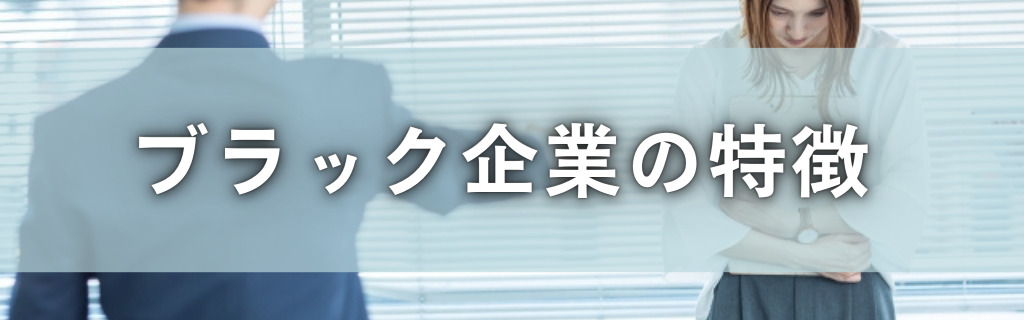
ブラック企業と呼ばれる会社は、具体的にどのような特徴を持っているのでしょうか。
下記のいずれかにあてはまる企業は、ブラック企業の可能性があります。
厚生労働省が規定する労働時間の原則は、下記のように定められています。
また、企業が時間外労働を命じられる「36協定(サブロク協定)」を結んでいたとしても、上限は月45時間・年間360時間です。
36協定を結ばずに厚労省の原則を超える、もしくは36協定の上限を超える労働時間だった場合は、れっきとした労働基準法違反といえます。
厚生労働省は、残業代についての規定を下記のように定めています。
時間外もしくは深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払う
また、既定の残業時間分の給料を含める「みなし残業」を導入していても、既定を超えた場合は残業代が発生します。
そのため、残業代が支払われないのは労働基準法違反です。
もし新入社員の数ヵ月での退職が頻発する場合は、会社の制度に問題がある可能性があります。
前職がホワイト企業だった人は、法律に則った労働環境に慣れているため、ブラック企業での勤務に違和感を感じやすいです。
単に仕事に合わなかっただけと片付けずに、会社の制度に疑問を持つ機会と捉えてみましょう。
ボーナスは会社の業績に応じて支払われるため、基本的に支給するかどうかは会社ごとに異なります。
もし就業規則や契約時効にボーナスの支給が明記されているのに支払われない、もしくは既定分に満たない寸志程度だった場合は違反行為です。
そのため、就業規則はあらかじめ確認しておきましょう。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、立派な人権侵害行為です。
もし職場で日常的にパワハラ・セクハラが行なわれているなら、従業員が完全に下に見られていると思っていいでしょう。
従業員への敬意を払えない体質の企業に対しては、証拠を集めて対抗しましょう。
一般的な企業では、年間休日数は120日ほどと言われています。
これよりも少ない休日数の会社は、休みが少ないと認識してもいいでしょう。
また、1日8時間の労働時間の原則に沿う場合、年間休日数は最低105日ほどです。
これを下回る休日数の会社は、労働基準法違反といえます。
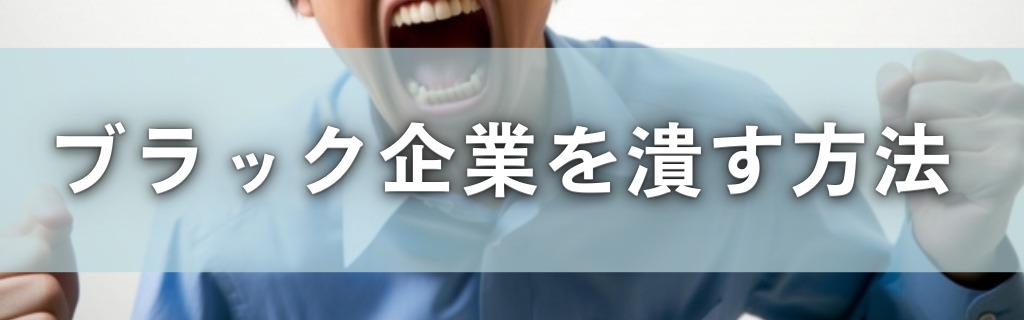
ブラック企業を潰すには、どのような方法を取ればいいのでしょうか。
合法的なブラック企業の潰し方をご紹介します。
ブラック企業の内情を、労働について公正な判断を下す外部機関に告発しましょう。
主な告発先は、下記の2つです。
労働基準監督署は、労働基準法に関する調査や違反企業への指導を行なう公的機関です。
厚生労働省の出先機関なので、いわば国に訴えるのと同じとも言えるでしょう。
ただし、決定的な証拠がない限りは動くことはありません。
そのため、労働基準監督署に訴える前には確実な証拠取りを行ないましょう。
労働局は、労働基準監督署の上部組織にあたる機関です。
労働基準監督署との違いとしては、パワハラ・セクハラへの対応も行なってくれる点です。
そのため、ハラスメントでお悩みの方は労働局に相談しましょう。
ただ、こちらも確実な証拠がないと動けないことは覚えておくべきです。
未払いの賃金や残業代は、証拠を集めることで企業に請求することが可能です。
労働時間に見合った給与の支払いを求めるために、下記のものを証拠として集めましょう。
重要なのは、労働時間を事実として示せるかどうかです。
正確な記録があることで、労働基準監督署や労働局を動かしやすくなります。
もしブラック企業を退職するとしても、1人辞めた程度では会社はすぐに代わりの人材を見つけてしまうでしょう。
ですが、ブラック企業も人がいなければ経営を続けることはできません。
退職によって少しでも損害を与えたいなら、同じ不満を持つ同僚と一緒に退職しましょう。
数人が結託して退職すれば、企業側はその穴を埋めるために人材を集める労力を余計に使います。
人材不足で適正な業務が行なえなければ、企業は大損害を被るでしょう。
独力ではなく、協力者を募って対抗するのも一つの方法です。
労働基準法違反の決定的な証拠が出れば、労働基準監督署や労働局も動かざるを得ません。
労働時間の記録に加えて、就業規則の内容も保管して勤務の実態と照らし合わせてみましょう。
それらを総合的に加味することで、外部機関を動かしてブラック企業に損害を与えられます。
ハラスメント行為については、労働基準法よりも刑法や迷惑防止条例で裁くことをおすすめします。
なぜなら、その内容は明確な犯罪行為だからです。
証拠については、音声をボイスレコーダーで隠し撮りすることをおすすめします。
自分と相手の会話を勝手に録音する「秘密録音」は違法ではないため、隙を見つけてボイスレコーダーを起動しましょう。
最近は小型のボイスレコーダーも多いため、ポケットに仕込むのも簡単です。
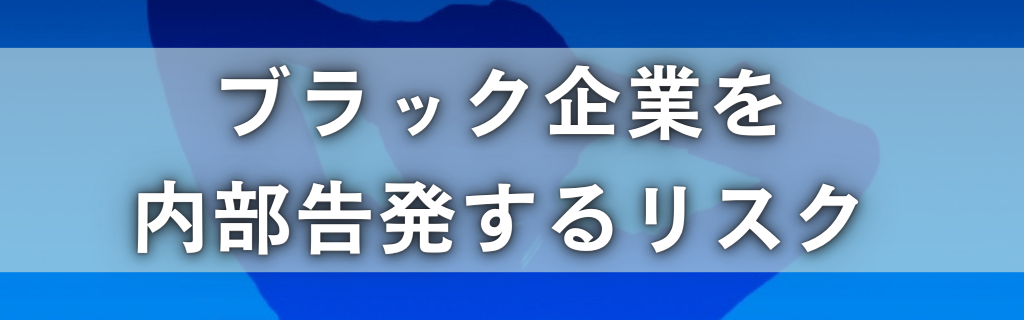
内部告発という行為は、告発前に発覚した場合のリスクも大きいです。
従業員は、会社にある種生殺与奪を握られているようなもの。
会社の対応は生活にも直結するため、内部告発のリスクは頭に入れておきましょう。
勤務先企業の違法行為を告発したことによる解雇は、当然ながら「不当解雇」にあたります。
よって、会社側はそれらしい言い訳をつけて解雇しようと試みます。
会社が従業員を解雇する方法は「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」のみであり、客観的・社会的相当性がなければ解雇権の濫用と判断されます。
また、懲戒解雇される場合でも客観的合理性と社会的相当性が必要で、会社の名誉を著しく傷つける犯罪行為や経歴詐称、度重なる無断欠勤を繰り返すなどの理由でなければ適用されません。
また、懲戒解雇を行なうには、あらかじめ対象時効を就業規則に明記する必要があります。
当然ながら、企業の不正行為を告発したことによる解雇は不当解雇と断言できます。
勤務先企業の違法行為を告発する際に最も注意すべき点は、SNSなどネット上への投稿が挙げられます。
例え違法行為が事実でも、業務や経営に関連する内容の書き込みは懲戒処分の対象となる可能性があります。
特に、経営者や経営幹部、同僚の従業員、取引先などの個人情報や名誉を棄損する内容を書き込むのは禁物です。
他にも、社外秘のノウハウなど会社の機密情報を漏洩した場合も、懲戒処分の対象となり得ます。
勤務先企業が違法行為をしているとわかっていても、証拠もなく安易に投稿すると、勤務先企業に大きな損害をもたらすでしょう。
そうなると会社側との信頼関係も壊れ、自身も懲戒処分を受ける可能性があると認識しておきましょう。
「SNSでは本名や勤務先を明らかにしていないから大丈夫」と思っていても、プロフィール内容や写真、過去の投稿から思わぬ形で特定されてしまうこともあります。

企業内に違法行為やコンプライアンス違反行為が存在する際、この事実を明らかすることで法令遵守を促進し、その法令を守ろうとした人の安全確保につながります。
このような観点から、内部通報者を保護する制度が公益通報者保護法です。
同法は、企業が内部通報者を解雇するなど不利益な取り扱いをすることを禁止しています。
加えて、内部通報があった場合に企業側が取るべき措置を定めています。
公益通報者保護法によって保護される「公益通報」は、「労働者」によるものでなくてはなりません。
ここでいう「労働者」とは、雇用主からの指揮命令を受けて業務に従事して賃金の支払いを受けている者であり、雇用形態を問わず「労働者」と定義されます。
一方で、退職している場合は雇用関係にないため、在職していた会社の違法行為を通報しても公益通報者保護の対象外です。
しかし、在職中に違法行為を通報した後に退職した場合は、労働者の身分を有する時点での通報となり公益通報の対象に含まれます。
よって、退職後に通報を理由として退職金を減額するような不利益の取り扱いは禁止されます。
通報対象事実は、まず違法行為を対象とします。
違法行為とは、公益通報者保護法が掲げる「通報対象」に該当する行為に限定されます。
最も効果的な通報先は、処分や勧告の権限がある行政機関に対する通報です。
もし通報者が誤って権限のない行政機関に通報をした場合、通報を受けた行政機関側は、どこの行政機関が権限を有するのかを教えてなくてはならないとされています。
そして、公益通報をされた行政機関は必要な調査を行ない、通報対象事実があると認めるときは法令に基づく措置を取らなければなりません。
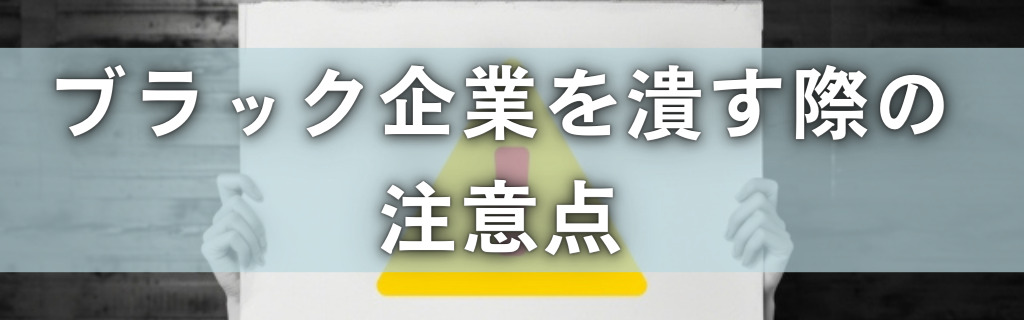
ブラック企業を潰す行動を取る際にも、注意すべき点はいくつかあります。
思ったような結果が得られないということは、出来る限り避けたいものです。
ブラック企業を告発する際の注意点を覚えておきましょう。
ブラック企業を潰すにしても、そのために他の社員に迷惑がかかる行為をするのは慎みましょう。
社員のなかには、生活のために会社で働き続ける意義を感じている人もいます。
また、恩義を感じている心優しい社員さんもいるでしょう。
「立つ鳥跡を濁さず」というように、出来る限り火種を広げない工夫も大切です。
ブラック企業を潰すという目標を掲げたとしても、相手が大企業である場合は難しいでしょう。
大企業は抱える社員数も多く、たとえ何人かが連れ立って退職してもすぐにその穴は埋まります。
また、労基法違反を告発しても信用が一時的に落ちる程度で、何年か経てば何事もなかったかのようになるでしょう。
もし相手が中小・零細企業なら規模が小さいため、一斉退職や労基法違反の告発は効果的です。
しかし大企業相手では、自分が被った損害分の補填を目指すのが現実的と言えます。
もし内部告発に向けた動きを察知されてしまうと、会社側が証拠の揉み消しを図る場合があります。
たとえば、決定的な証拠を社内のパソコンに保存しておくと、知らぬ間に消されてしまうことも。
また、タイムカードや業務報告の内容を改ざんされる可能性もあるでしょう。
証拠は会社の外に保管しておくことを徹底しましょう。
勤務先企業の違法行為を、自らの身分を守った上で告発するのは勇気が必要ですが、以下のような窓口に相談しましょう。
その他の政府機関や各都道府県の弁護士会、自治体などに訴えるのもひとつの手です。
同じ会社からの被害の報告が数多く寄せられていれば、そうした機関が働きかけをしてくれる可能性もあるでしょう。
また、被害者同士で連携しての集団訴訟提起などの手段も考えられます。
それでも解決が難しく、訴訟問題に発展しそうなほどのトラブルに巻き込まれたときは、企業・団体調査の専門家である嫌がらせ対策専門窓口にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、被害の状況、対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口