“ウソも100回言えば真実になる”といった人間の心理を突いて、疎ましく感じる人物についてネガティブなウソ情報を流して、孤立化を図る、人間関係の“壊し屋”といえる人物がいます。
悪い噂を流されている人が知らない間に、伝聞、あるいはネット空間などで、根も葉もない話を広められ、気がつけば、その噂が独り歩きし、孤立無援の状態に追い込まれていた…などということも起きています。
このような悪質な嫌がらせをはたらく人を「コミュニティ・クラッシャー」と呼び、住まいや会社・学校などの組織の中には、一定程度、存在するものと考えられています。
こうした人間関係の破壊を目的としたウソ情報を流す嫌がらせに対し、どう対処すればいいのか、解説します。
「壊し屋」とは、人間関係を意図的に破壊する役割を果たす存在です。
彼らは通常、他人の関係や結びつきを悪化させるために行動します。
目的は、友情や家族の絆、パートナーシップ、労働関係などの関係を解消し、不和や混乱を引き起こすことです。
壊し屋は、個人的な利益や報復、または他の人々の関係に対する嫉妬や敵意から動機づけられることがあります。
彼らは陰湿な手法や計略を使い、嘘や中傷、隠し事、または他の人々の信頼を裏切る行動を通じて、関係を壊そうとします。
壊し屋は、関係の破壊によって他者に苦痛や悲嘆をもたらし、社会的な結びつきを崩壊させる可能性があります。
ターゲットの人物に関するネガティブが噂を流して、人間関係を壊そうとする人は、総じて「自己中心的」です。
しかしながら、そんな人に限って、自分が自己中であることに気付いておらず、自分が悪いことをしている、迷惑をかけている自覚がなく厄介です。
そのような人物は、常に“自分軸”でしか物事を見られない傾向があります。
「相手にしていることを自分がされたらどう思うのか?」という考えに至らないことも多いのです。
また、自己中の人は、相手がどう思うかより「自分の都合」「自分の心地良さ」を悪気もないまま優先します。
だからこそ、ときとして、自己中心的な考えに基づいた、隣近所の悪口を触れ回り、気が付けば、それが真実とされ、近隣住民との関係に悪い影響を及ぼすこともあり得るのです。
ただし、自己中の人は、視野が狭いというだけで、別に意地悪でやっているということもあります。
本人に悪気がない分、自分がやっていることの過ちに気付いていないことが多く、だからこそ、解決するには厄介なことも多くあります。
伝聞による悪口がトラブルの発展する事象は、隣近所に限った話ではありません。
その代表的なものが、子どもを通じたママ友とのトラブルがこじれてしまうケースです。
例えば、子ども同士のトラブルが原因で感情的になってしまったり、家庭の事情を広められてしまったり、SNS上などで悪口を書かれてしまったりなどのトラブルがあります。
被害を受けた側のなかには、誰にも相談できず、うつ病に追い込まれてしまうケースもあります。
会社などの組織においての嫌がらせの代表格は「パワーハラスメント(パワハラ)」でしょう。
厚生労働省では、パワーハラスメントを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義していますが、これには身体的攻撃や精神的攻撃、不当に過大な(あるいは不当に過小な)業務命令のみならず、「一人だけ別室で仕事をさせられる」「仕事を手伝ったり、手伝ってもらったりできないよう指示する」「懇親会などに出席できないようにされる」など、対人関係を阻害し、孤立させる行為もパワハラに該当します。
また、業務に必要な資料などを閲覧させないなど、仕事に支障をきたすような、タチの悪いパワハラも存在します。
このようなパワハラ行為の中には「プライバシーの侵害」も含まれており、「机や私物を物色される」「恋人や家族のことをしつこく聞かれる」ことに加え、「社内の人間に、当人あるいは恋人や家族の悪口を言う」「知られたくない秘密を漏らす」「有給休暇を取る際に宿泊先や同伴者を尋ねられる」といった行為もパワハラに該当します。
当然ながら、ありもしない悪評を社内に広められる行為によって、被害者が社内で孤立させられる事象はパワハラ行為といえる悪質な人権侵害です。
ネット上には虚偽と事実、さらには事実のように書かれた個人の意見など、さまざまな情報が玉石混淆にひしめき合っています。
だからといってネットから情報を得ないわけにはいきません。
そもそも、「フェイクニュース」という言葉もある通り、その情報の出どころがマスメディアであってもその内容を100%信頼できる時代ではなくなってきています。
ある国際比較では、日本人は比較的、フェイクニュースに騙されやすく、加えて、若い世代ほど、その傾向が強いという結果が示すように、デジタルリテラシーの欠如によって、ウソ情報に翻弄されている姿が見え隠れします。
特にSNSは、その匿名性から、簡単にウソ情報を流布させることが可能となってしまっている現実があり、ときとして、その対象が一般の一個人に向けられることもあります。
ネット上、特にSNS上で、家族や交際相手に関するネガティブな情報を目にしたとしたら、その内容が100%虚偽であったとしても、“火のない所に煙は立たぬ”とはいえど、思わず対象者を疑いの目で見てしまうこともあるでしょう。
しかしながら、“火のない所を炎上させる”のがネット空間の特徴ともいえます。
これを悪用して情報操作を施し、人間関係を悪化させようとする“別れさせ屋”といった悪質な業者も存在します。
「人間関係にストレスを感じる」という人のなかでは、「家族関係にストレスを感じる」割合も多く、その多くが女性であることがわかっています。
コロナ禍によるリモートワークの定着によって、この傾向は顕在化し、さらに、時間の多くをともにする家族がストレスの原因になると、逃げ場もなく、そのストレスは、解消する場がないどころか、よりいっそう大きくなります。
本来安らげる場であるはずの家庭が、うつ病を発症してしまう原因になり、引きこもったり、あるいは攻撃的になってしまうことも少なくありません。
こうした、家族関係に関してストレスを感じる人は、いわゆる「コロナ離婚」に至ったり、若い世代は、半ば家出状態で新宿の“トー横”に代表される繁華街をたまり場とする問題も出てきています。
これらも、家庭でのストレスによる家庭崩壊が引き起こした現象といえそうです。
人間関係を壊してしまう人は、自分軸のみで物事を考え行動する傾向があります。
その本人はそれが正しいと思っているので、周りに迷惑をかけている現実に気づくことも難しいでしょう。
被害に遭っている人が身近にいたら「味方になる」「その人の言い分を認める」「細かいことは気にしない」ことを念頭に置いて、できるだけストレスを遠ざけ、相手を尊重し理解しようとする努力が重要です。
人間関係トラブルなどについては、以下のような相談窓口が用意されています。
その他、各都道府県の労災病院や精神福祉保健センターなどでも相談窓口を設けています。
また、職場などでの問題では、労働基準監督署やハローワーク、法テラスでも相談を受け付けています。
それでも解決が難しく、悪口のレベルを超える嫌がらせなどのトラブルに巻き込まれたときは、嫌がらせの証拠収集専門家である対策専門窓口にご相談ください。
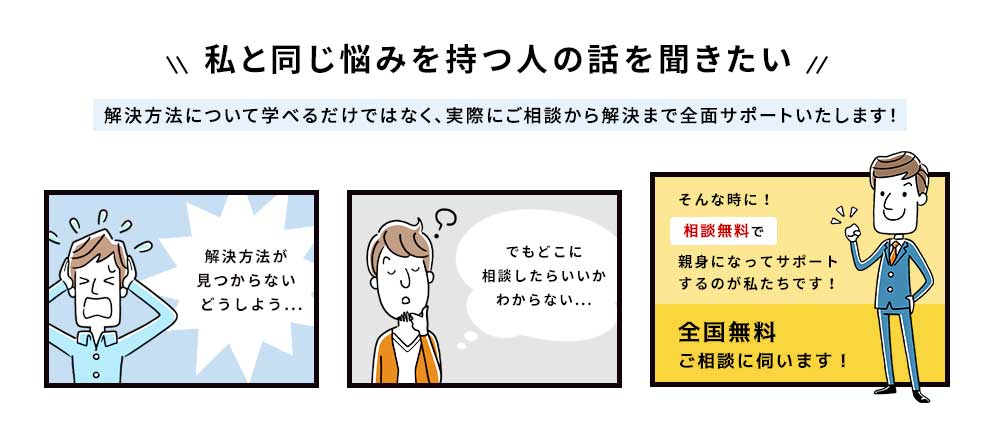
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口