ストーカー被害に悩まされている方々へ、ストーカー規制法の禁止命令と罰則について詳しく解説します。
この法律は、被害者の安全を守るために制定されたものであり、具体的な禁止命令の内容や、違反した場合の罰則について知ることで、より効果的に対策を講じることができます。
この記事を参考に、ストーカー被害から自分や大切な人を守りましょう。
目次 [ 閉じる ]
ストーカー規制法は、ストーカー行為を防止し、被害者を守るための法律です。
この法律は、ストーカーによる追跡、監視、脅迫、付きまといなどの行為を禁止し、被害者の安全を確保するための措置を提供します。
ストーカー規制法に基づき、被害者は裁判所から禁止命令や接近禁止命令を受けることができます。また、違反者には罰則が科されることがあります。
ストーカー行為に悩む人々にとって、この法律は重要な法的手段となります。
令和3年5月26日にストーカー行為等に関する法律の一部が改正されました。
この改正内容は同年6月15日から施行され、職場や学校、住居などの通常の拠点以外にも、被害者が実際にいる場所の付近も規制対象に追加されました。
さらに、同年8月26日の改正では、車両などに取り付けたGPSを使って、本人の許可なく特定人物の位置情報を取得する行為も新たに規制対象となりました。
ストーカー規制法の改正により、被害者の安全をより一層確保するための措置が強化されています。
ストーカー規制法における禁止命令は、被害者を保護するための重要な手段です。
この命令は、ストーカーからの接触や連絡を制限し、被害者の安全を確保することを目的としています。
禁止命令とは、都道府県公安委員会によって発行される、つきまとい行為などを抑止するための処分です。
被害者の安全を守るための法的な手段であり、この命令に違反すれば罰則が科せられることもあります。
被害者がストーカーからの保護を求める際には、禁止命令の申請を検討することが非常に重要です。
これにより、ストーカー行為から身を守るための法的なサポートを受けることができます。
接近禁止命令は、禁止命令よりもさらに具体的な措置です。
この命令は、特定の場所や距離に関して、ストーカーが被害者に接近することを禁止します。
具体的には、以下のような制限を課します。
接近禁止命令は、より直接的に被害者の安全を確保するための措置であり、被害者に対する物理的な接触や接近を防ぐことを目的としています。
こちらも違反者には罰則が科されます。
ストーカー行為をした人は一年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
口頭警告や文書警告は警察がストーカー規制法4条により被害届からの申し出に基づいて警察本部長が行為者に交付します。
禁止命令はストーカー規制法5条により被害者からの申し出や職権により付き纏い行為者への行政処分となります。
禁止命令違反は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ストーカーと禁止命令両方違反の場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。
ストーカー被害による損害賠償や謝罪金は弁護士が仲介することで民事上の損害賠償責任として加害側に支払い命令が出ます。
そのためにも以前から警察へ相談し、被害届を書くことが重要になってきます。
証拠(第三者取得と証明)に基づき加害相手に損害賠償責任を取らせることができます。
平均額150万円以上になるケースは、「念書を交わしてもストーカーを続けた場合」「被害者が精神疾患を患うことで生活に支障をきたした」などがあります。
落ち度が全くない前提ですが、慰謝料が200万~300万、悪質ですと750万円の金額も見受けられます。
大概、示談(弁護士と加害者の話し合いで裁判をせずに金銭で解決)による解決となっています。
最近のストーカー被害は、SNSで出会ったり、配信者と視聴者の関係など、インターネット環境に起因することが多くなっています。
SNSを通じたコミュニケーションは、直接会うことなくダイレクトにオンオフの関係が続くため、関係が断ち切れにくい特徴があります。
これは、従来の直接的な関係が徐々にフェードアウトする形とは異なり、オンラインで繋がっている限り関係が続いてしまうため、ストーカー行為が長引くことがあります。
その反面、SNS上でのストーカー行為は記録が残りやすく、メッセージのスクリーンショットなどが証拠として役立つため、自分がストーカー被害に遭っていることを他人に説明しやすい利点もあります。
現在では、通りすがりに突然ストーカーされることは少なく、主にSNSでの人間関係がストーカー行為の発端となることが多いです。
学校や職場などの活動の場以外でも、SNSでの出会いがストーカーと出会う主な原因となっています。
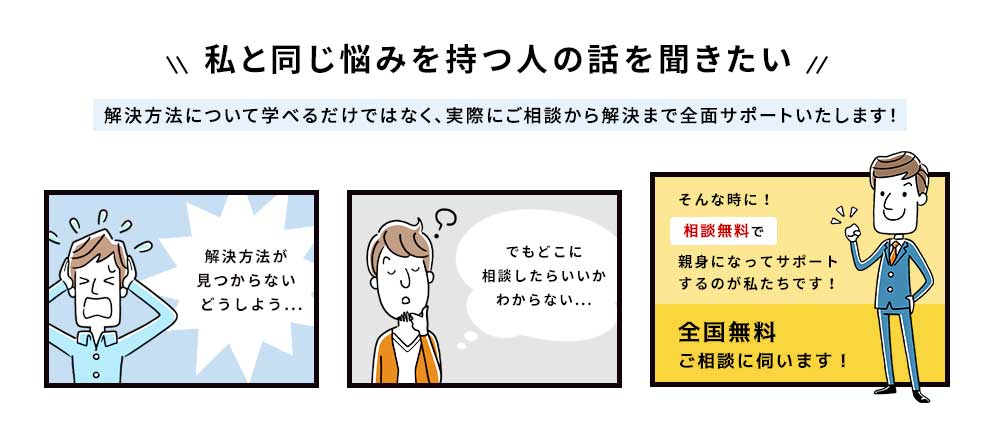
ストーカーに悩んでいる方へ、まずは一人で抱え込まずに誰かに相談することをお勧めします。
家族や友人、信頼できる人に相談し、助けを求めることが重要です。
また、警察や専門の相談機関に相談することも一つの選択肢です。
自身の安全を最優先に考え、周囲のサポートを受けながら適切な対策を取ることを心掛けましょう。
困ったときには、お気軽にご相談ください。
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口