現代の脅威として、ストーカー行為が深刻な社会問題となっています。
ストーカーは被害者を執拗に追跡し、嫌がらせや監視を行い、心理的な苦痛や恐怖を与えます。
SNSやテクノロジーの発展により、ストーカー行為の手段や範囲が広がっています。
被害者は早期に警戒し、サポートを受けると共に、法的な措置を講じる必要があります。
社会全体でストーカー問題に対処し、被害者の安全を守る取り組みが求められています。
目次 [ 閉じる ]
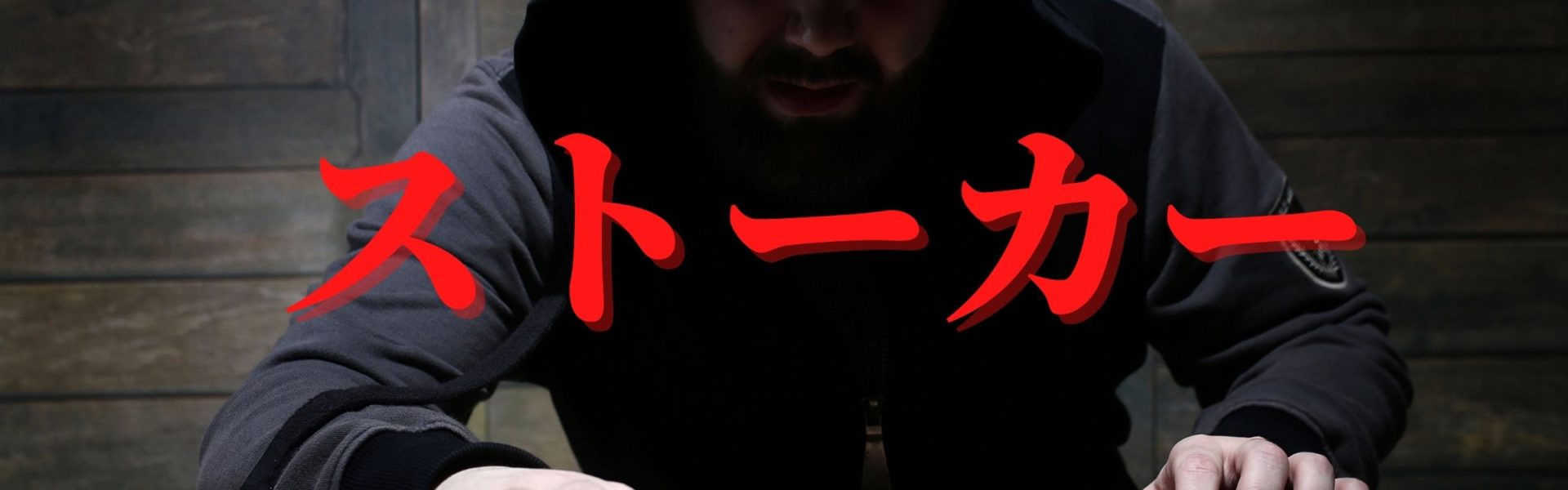
「ストーカー」という言葉が日本で定着したのは1990年代。
それ以前は「変質者」、知り合い同士による付きまといなどであれば「痴情のもつれ」として、警察で取り締まることはありませんでした。
それが、1999年に女子大学生が元交際相手の男性を中心とするグループから嫌がらせ行為を受け続けた末に埼玉県のJR桶川駅前で殺害された、いわゆる「桶川ストーカー殺人事件」がきっかけで、警察の対応や遺族への報道被害など、法整備への機運が高まり、「ストーカー規制法」が議員立法により誕生しました。
しかしながら、その後も、警察の「民事不介入」名目の怠慢によるストーカー被害は相次ぎ、不幸な事件が相次ぐ事態となりました。
現代のストーカーになりやすい人の特徴は、個人によって異なりますが、以下のような特徴が関連する可能性があります。
コントロール欲の強さ
ストーカーになりやすい人は、他人を支配しようとする強いコントロール欲を持つ場合があります。
彼らは被害者の行動や関係をコントロールしようとし、支配欲を満たすためにストーキング行為に走ることがあります。
対人関係の問題
ストーカーになりやすい人は、対人関係において問題を抱えていることがあります。
孤立感や拒絶感を抱えていたり、対人コミュニケーションのスキルに欠けていることが考えられます。
妄想や被害妄想
ストーカーになりやすい人は、妄想や被害妄想に囚われる傾向があります。
彼らは非現実的な信念を持ち、被害者に対して敵意を抱いていると誤解し、ストーキング行為に走ることがあります。
自己中心的な思考
ストーカーになりやすい人は、自己中心的な思考を持っていることがあります。
彼らは自分の欲望や目的を優先し、他人の感情や権利を無視する傾向があります。
過去のトラウマや心理的な問題
ストーカーになりやすい人は、過去のトラウマや心理的な問題を抱えていることがあります。
これには、虐待の経験、不安や抑うつ症状、人間関係の困難などが含まれます。
これらの特徴があるからといって必ずしもストーカーになるわけではありません。
しかし、これらの特徴が相互に組み合わさる場合、ストーカー行為に走るリスクが高まる可能性があります。
ストーカー行為は深刻な犯罪であり、被害者の安全を守るためには予防や早期の対応が重要です。
まず、ストーカーの思考回路は一般人たちとは違い、常識が通用しないことがあるということを認識しておく必要があります。
それは「依存、執着心が“異常に”強い」「思い込み、妄想が“異常に”激しい」「自らの非を“異常に”認めない」といった特徴があります。
交際を申し込まれたものの、断られたとしても「好意がないはずがない」「誰かが邪魔をしているの」「その邪魔な相手がいなくなれば自分と付き合ってくれるはず」と信じて疑わず、執着してきます。
また、逆恨らみ、怨恨に発展しストーカー化するケースもあります。
そして、ストーカーは自身の行動を正当化しようとする傾向があります。
彼らは被害者に対して自分たちの行動の合理性や正当性を信じ込もうとし、自己を正当化しようとします。
やってはいけないストーカー対策には以下のようなものがあります。
自身が被害者となっているからといって、ストーカーに対して復讐や報復を行うことは法的にも倫理的にも問題があります。
自力での対抗は状況を悪化させる可能性があります。
ストーカーとの直接的な対決や対話は危険です。
ストーカーに対して自身の感情や怒りを伝えることは、彼らの興味を引き、彼らの行動を継続させる可能性があります。
自己防衛は重要ですが、ストーカーに対して暴力を振るうことは法的な問題を引き起こす可能性があります。
自身の安全を確保するためには、法的な手続きや専門家の支援を求めることが重要です。
ストーカーは被害者の反応や関与を求める場合があります。
そのため、ストーカーの行動に対して直接的な反応を示すことは避けるべきです。ストーカーの行動に対しては、警察や専門家の助けを借りて適切な対策を講じるべきです。
ストーカーが被害者の周囲の人や協力者に対して報復を行うことがあります。
被害者自身や関係者が報復やストーカー行為に関与することは、問題を悪化させる可能性があります。
周囲の人々も安全を確保するために、ストーカーの行動を報告し、適切な支援を受けるべきです。
これらの行動は問題を悪化させるだけでなく、法的な問題を引き起こす可能性があります。
Q
ストーカーはどのような行動をするのですか?
A
ストーカーは被害者を執拗に追いかけ、監視や嫌がらせを行います。具体的な行動には、被害者の身辺や行動の監視、メッセージや電話の嫌がらせ、プライバシーの侵害、被害者の家や職場への付近での待ち伏せなどが含まれます。
Q
ストーカーになる要因は何ですか?
A
ストーカーになる要因は人それぞれです。一般的な要因としては対人関係の問題、支配欲やコントロール欲の強さ、過去のトラウマ、自己中心的な思考、妄想や被害妄想などが考えられます。
Q
ストーカー行為の被害者はどのような苦痛を経験するのですか?
A
ストーカー行為の被害者は、恐怖感や不安、プライバシーの侵害、社会的な妨害、心理的なストレス、身体的な危険を経験することがあります。被害者は自由や安全が脅かされるため、日常生活や精神的な健康に重大な影響を受けることがあります。
Q
ストーカーに対してどのように対処すれば良いですか?
A
ストーカーに対処するためには、以下の対策を検討することが重要です。警察への相談、被害の証拠の収集、プライバシーの強化、サポートグループや専門家の支援の利用、関係当局への報告などです。安全を確保するためには、自身の状況を正確に把握し、必要な措置を講じることが重要です。

監修者・執筆者 / 山内 / 2024年6月17日更新
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口